
土地を購入する際に、意外と忘れられがちなのは、その場所における天災リスクについて調べることです。
天災、具体的には、洪水、土砂災害、高潮、津波などのリスクを記した「ハザードマップ」が公開されています。
このハザードマップについての見方や重要性を知ることで、土地を違った角度でチェックすることができます。
国土交通省運営の「ハザードマップポータルサイト」から、マイホームの候補地の周辺で、どのような災害が起こりうるのか、調べるクセを付けましょう。
国土地理院では、
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図
と記されています。
別称としては、防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどが使用されているケースもありますが、目的は変わりません。
ハザードマップは、前述した国土交通省の運営の他に、各自治体でも公開されていますし、NHKでも公開しています。
ここ近年、日本列島で災害が多発しており、ハザードマップはこれまで以上に土地を決める際の重要資料になっています。
まさに、土地の選び方のポイントはハザードマップで危険情報を知ることであり、事前にリスクを知る上で欠かせないものとなります。
以降、この記事では、国土交通省運営の「ハザードマップポータルサイト」を中心に解説していきます。
まず、ハザードマップポータルサイトには、2種類存在します。
「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」というものです。

違いとしては、
となります。
わがまちハザードマップは、各自治体の公式サイトにジャンプしての閲覧となりますが、今、住んでいる地域ごとに様々な種類のマップを見ることができます。
「まちを選ぶ」という項目から、住んでいる都道府県と市区町村をプルダウンメニューで選択して使用します。
移住先として気になる地域のリスクを知る場合も便利です。
一方、「重ねるハザードマップ」は、
この6つの中から知りたい情報を選択することができます。
住所(エリア)を入力してマップを表示した後は、最大6種類の情報を同時に表示できるしくみになっています。
ゆえに「重ねるハザードマップ」と呼ばれるわけです。
山が多いエリアは「土砂災害」、海が近いエリアは「津波」など、住んでいるエリアや検討しているエリアごとに、表示を切り替えて確認してみましょう。
土地選びは、どうしても物件情報だけに着目しがちなため、ハザードマップを見たことが無い、あるいは知らないまま土地を購入しようとする人は多いです。
確かに、これまで災害とは無縁だった場合は、つい、見過ごしがちになりますが、異なるエリアに住むのならば、少なくとも一度はハザードマップでのチェックは欠かせません。
ただし、ハザードマップ上でリスクが高いとされる土地であったとしても、その分、価格設定においては割引など、期待できないことを念頭に置いてください。
あまりハザードマップに囚われすぎて、あれこれ迷っていると、その間に購入者が決まってしまう恐れもあります。
「重ねるハザードマップ」だけでなく、時には「わがまちハザードマップ」の災害種別から、地盤被害(液状化)など土地に関わる事例をチェックしてみましょう。
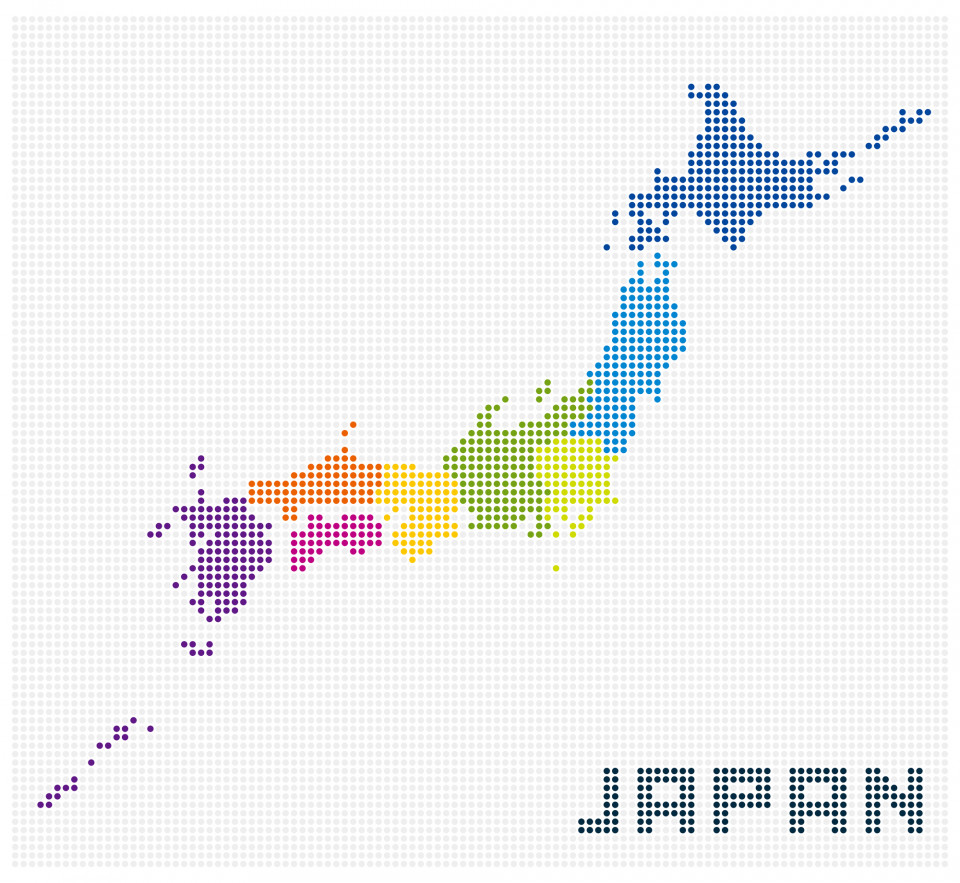
土地に関する災害として地盤被害(液状化)を取り上げてみます。
改めて見方を説明すると、「わがまちハザードマップ」で「地図で選ぶ」を選択し、メニュー「災害種別から選択する」にて「地震防災・危険度マップの公表状況を見る」を選択します。
さらに「地盤被害(液状化)マップ」を選択すると、公表している自治体が青色で表示されます。
当社リブワークの本社がある熊本県では、熊本市、宇城市、八代市が公開中です。
液状化マップ(以下、同表記)を見ると、自治体によって異なりますが、いくつかの段階で表示していることが多いです。
熊本市を例に挙げると、液状化の可能性を、
と、5段階になっています。
可能性ごとに色分けされており、一目で対象エリアがわかるようになっています。
ここで、液状化マップを見る時に、気をつけて頂きたいことがあります。
液状化マップだけでは、地盤の強弱は判断できないということです。
そもそも液状化は、地震発生において、
砂の粒同士が離れて、水に浮いた状態になる
ことを指します。
引用:熊本市 液状化ハザードマップ
※熊本市ホームページは令和7年1月にリニューアルしました。
それゆえに、
という状態もあります。
実際に、
「液状化の可能性が低いエリアだったから購入したのに、いざ地盤調査をしたら地盤改良工事が必要で追加費用がかかった...」
「液状化=地盤の強弱かと思って、地盤改良工事費を予算に入れておらず予想外の出費になった...」
などということも起こりますので、液状化マップで全てを判断するのではなく、あくまでも可能性のレベルで情報を入手してください。
可能性を示すものではありますが、やはり地震大国のわが国において、可能性の高いエリアは不安に感じるものです。
対処法としては、
があります。
直接、当該エリアに出向いていくことは、あまり効率的ではありませんので、自治体のハザードマップを管理している部署に問い合わせをしてみることも、ひとつの手段です。
また、不動産業者やハウスメーカーにも聞いてみる価値はあるでしょう。
液状化を防ぐ工事とは、さまざまな工法が存在し、戸建て向けとしては、
などがあります。
参照:新築住宅の液状化対策とその費用|復旧・復興支援WG「液状化被害の基礎知識」
しかし、この液状化対策工事は、費用の負担が数百万レベルのため、必要と判断するには悩ましいものになります。
建築士やハウスメーカーとよく相談してみましょう。

ハザードマップは天災リスク情報のみを提供しているわけではありません。
突然の天災によって、自分の身を守る必要がある場合に備えての情報も入手することができます。
例えば「重ねるハザードマップ」の道路防災情報だと、
といった情報がマップ上で表示可能です。
具体的にはアンダーパスなど、大雨の際に冠水して車両が水没するなどの事故の可能性がある場所などが示されます。
局地的な豪雨による被害が拡大傾向にあるため、道路関連の情報は、土地探し以外でも定期的に目を通しておくと良いです。
洪水、土砂災害、高潮、津波情報を選択すると、「指定緊急避難場所」を表示することができます。
マップ上に人が走っているようなピクトグラムが現れ、それを選択すると、
を確認できます。
購入予定の土地から指定緊急避難場所までの避難経路など、ハザードマップ上で見ておくと良いです。
実際に、現地を確認した際にでも、時間があれば避難ルートを歩き、避難場所を見てみることも実生活がより想像しやすくなります。

2020年8月28日より、不動産取引の際は、水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップを提示して、対象物件の所在地を事前に説明することを、宅地建物取引業者に対して重要事項説明として義務付けされました。
ゆえにハザードマップを見る機会は、少なからず土地購入の検討をしていれば、一度は目にすることになります。
しかし、いざ契約目前となってからハザードマップを見せられても意味はありませんので、自ら積極的に情報は取りに行くべきです。
義務化を公表した国土交通省は、以下のように背景を説明しています。
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年7月(2019年)に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、今般、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することといたしました。
引用:宅地建物取引業法施行規則の改正について - 国土交通省
近年の大規模災害において、残念ながら被害に遭ってしまった方の談話には、
「今まで何十年と住んでいたが、こんなことは初めてだ。」
といったことが目立っています。
またメディアでは「想定外」という言葉で、その被害の尋常さを伝えてはいますが、果たして本当に想定外なのかどうかを検証した結果は、伝えられることはありません。
もしかすると「歴史は繰り返す」ではありませんが、実際には過去に似たような災害が繰り返されている事実があるかもしれません。
ゆえに、これからはハザードマップが、ますます土地探しや購入に置いて、重要な資料となることは間違いありません。
水害ハザードマップを提示して、対象物件の所在地を説明することの義務化は既に施行されていますが、自治体によってはハザードマップの整備が追い付いていないケースも想定されます。
万一、自治体が作成したハザードマップが無い場合、不動産業者の対応が気になるところでしょう。
実は、「提示できるハザードマップがこの地域には無いのです」と購入希望者に説明すれば、宅地建物取引業者としては役目を果たしていることになるのです。
しかし、前述した「ハザードマップポータルサイト」は水防法に基ずくものですから、おそらく不動産業者側も、そこから情報を引っ張ってくるものと推測します。
詳細については、「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A」をご覧ください。
参照:宅地建物取引業法施行規則の改正について - 国土交通省

以上のようにハザードマップは、土地取引には重要なものとなっています。
土地の選び方のポイントは、改めてハザードマップで危険情報を知ることであると、お伝えしておきます。
ハザードマップについては定期的に更新されるため、常に最新情報を見るように心がけると良いでしょう。