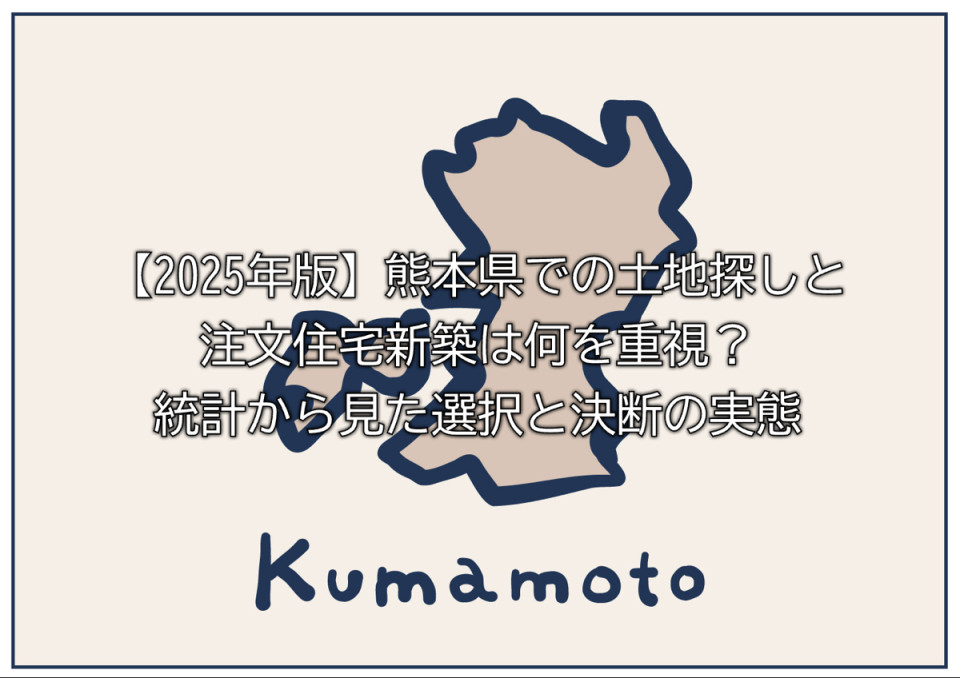
熊本県での大規模な地震発生(平成28年熊本地震)以降、注文住宅で重視したいことに「耐震性」を挙げる声は少なくありません。
全国的にも、耐震性の高さを住宅仕様の優先事項として求める人が増えているのは、不動産情報サービスの調査でも明らかになっています。
安定した耐震性を維持するためには、土地選びも条件や確認すべきポイントがあります。
この記事では、注文住宅での優先事項について、まとめて紹介します。
注文住宅に高い耐震性を求めるのは、今や当たり前の時代となっており、各ハウスメーカーも大地震に耐えられる強度や、揺れにくい構造に力を入れています。
注文住宅を検討する人も、耐震性についての関心の高さが伺えます。
この章では注文住宅の建築における耐震性への意識変化や、他の条件との関連性について言及します。
熊本地震を振り返ってみると、地震の規模を示すマグニチュードは6.5、最大震度は益城町で記録した震度7でした。
しかも震度7の揺れが28時間以内に2度発生したことが特徴で、強い余震も度々発生し、過去に類を見ないほど短期間で頻発した類まれなる大地震として地元の人々のみならず全国の人々の記憶に残っています。
主な震度と発生回数は以下の通りとなっています。(2016年4月14日~7月2日)
震度7:2回
震度6強:2回
震度6弱:4回
震度5強:5回
震度5弱:14回
トータルで27回、震度3以上となると510回にもおよび、福岡県の北部にもその揺れが伝わってきたという声も聞いています。
耐震性能に劣る古い建物をはじめ、20万棟近い建物に被害が生じたこともあり、耐震性についての考え方が大きく変わったきっかけと言っても過言ではありません。
現に、アットホーム(株)が公開している「注文住宅を建てるまでの実態調査」では、約55%の人が耐震性に優れていることを建築で重視したいと回答しています。
注文住宅に高い耐震性を求めるのは熊本県民のみならず、必要性に対しては全国的に関心が寄せられているのが実態です。
注文住宅で求められる性能としては、断熱性・収納・間取りの動線などがありますが、耐震性より優先順位が下がりつつあります。
快適な生活環境を作り上げたとしても、地震で建物が倒壊してしまえば、すべて意味がなくなってしまうため、大前提として家族が長く安全に暮らせる仕様を求める意識が強まったといえます。
ハウスメーカーとしても建築した注文住宅が地震で倒壊してしまうと、これまで築き上げた信頼と実績も崩れてしまい、イメージダウンも避けられません。
世間的な評価も下がればますます信頼の回復が遠のくことから、構造の開発・研究だけでなく、耐震性を発揮できる設計に取り組んでいます。
南海トラフ地震の発生も予想されていることから、生活環境の良さと耐震性とのバランスを取ることが重要視されると考えます。
注文住宅なら、まずは熊本エリアのおすすめ土地情報をチェックしましょう。

耐震性の高い注文住宅を建てるのであれば、土台となる土地の地盤強度も確認が必要です。
地盤が軟弱であれば、地震発生時に耐震性が発揮されない恐れがあり、土地ごと崩れてしまう事態は避けなければなりません。
地震に強い家を建てるのであれば、土地探しの時点から地盤のチェックは必須です。
この章では、具体的に立地上のリスクを知る方法や、土地探しで考えるべき条件について紹介します。
熊本県は比較的強固な地盤ですが、仲新町付近は埋め立て地のため液状化の不安要素があります。
最大震度を記録した益城町は布田川(ふたがわ)断層帯上に位置し、さらには町を起点として南西方向に日奈久(ひなぐ)断層帯があるエリアです。
まずは、地盤が強く液状化のリスクが少ないエリアを知ったうえで、ライフスタイルに合う環境が得られそうな土地の選定をしましょう。
地盤や液状化に関する情報は、各自治体からハザードマップが公開されています。
自ら閲覧・確認したうえで、不動産会社やハウスメーカーの補足情報があれば、土地選びの軸がぶれなくなります。
建築を依頼するハウスメーカーが決まっていれば、希望する土地周辺での地盤調査の有無や建築事例の紹介も有益な情報です。
ハウスメーカーは地盤調査や建築時の改良工事についてデータを保管しており、近くで建築していればある程度の地盤データを入手することができます。
地盤以外にも洪水や内水、高潮に関する情報が公開されていますので、災害時のリスクについての事前調査が重要といえます。
半導体受託製造最大手のTSMC進出・稼働を経て第二工場建設の年内着工、東京エレクトロンの工場拡張といった半導体バブルの影響によって、周辺の地価は大きく上昇しています。
住宅需要の高まりによって阿蘇郡西原村では、400~500世帯規模の大規模な住宅用宅地開発が検討されています。
また、主要な工場が集積している菊陽町・大津町の坪単価が急上昇しており、住宅需要と相まって県内で最も街が活性化している自治体として注目の的です。
熊本県は半導体工場の集積地としてポテンシャルがあり、長閑なエリアでも将来的には市街化への開発がスタートすることも予想されます。
土地探しをする際には、将来の資産価値という視点で検討してみる価値はあります。
再開発の情報は、不動産会社や熊本県の建築課から入手することができますので、定期的にコンタクトを取ってみるのもおすすめです。
再開発で伸びそうなエリアに、新着の土地情報が続々と公開されている物件サイトが便利です。

耐震性の次に重視するポイントとしては、何が最適なのかは、世帯や建築主個々の考え方で異なります。
一般的には断熱性・気密性・省エネのほか、ムダのない動線の間取り、日照や景観の確保などが挙げられますが、熊本県は阿蘇山と熊本湾に挟まれていることから、エリア独自の環境への対応が必要です。
国の指針として2030年以降の新築住宅においては、ZEH水準の省エネルギー性能が求められるため、最低限の目指すべきレベルといえます。
ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、住宅で消費されるエネルギーよりも太陽光発電などで創出されるエネルギーが上回るように設計され、1年間で消費するエネルギー量を実質的にゼロ以下にする住宅のことです。
2025年4月以降に建築される新築住宅は省エネ基準への適合が義務化されており、断熱性能等級4以上が求められていますが、2030年以降ではZEH水準が義務化されます。
ZEH水準の断熱性能がある住宅は、エネルギー利用を効率化し、夏は涼しく冬は暖かい環境を保ち、室内の温度差を少なくできるため身体に無理な負担が及びません。
室内の温度差が少なければ、冬時期特有のヒートショックを防げます。
さらにZEHでの住宅建築にあたっては、補助金制度が公開されており、ZEHの種類に応じて以下のような金額を受け取れます。
|
ZEHの種類 |
1戸あたりの補助金額 |
|
ZEH、Nearly ZEH、ZEH Oriented |
55万円 |
|
ZEH+、Nearly ZEH+ |
90万円 |
※詳細はZEH補助金の公式サイトをご覧ください。
住宅仕様において耐震性に納得できれば、断熱性と省エネ性を優先し、家族全員が気持ちよく生活できる空間の実現に注力することが重要だといえます。
住宅性能を総合的かつ客観的に判断する方法として、住宅性能表示制度があります。
住宅性能表示制度とは、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度となっており、以下の3つが目的です。
新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
国土交通省に登録された第三者機関が・構造の安定・劣化対策・省エネルギー対策など10分野33項目で評価を行い、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類を評価結果として交付するしくみです。
制度の利用で、住宅ローンの金利優遇や、耐震等級に応じた火災保険料(地震保険料)の減額といった特典が受けられます。
住宅性能表示制度の利用で住まいの性能を数値や等級で見える化しておけば、将来の売却や賃貸市場において高評価を得られる可能性があります。
あくまでも利用は任意ですが、評価を希望する場合は、時間とコストが必要です。

熊本地震だけでなく、令和6年に発生した石川県の能登半島地震によって、ますます大きな地震に対して危機感や防災意識を持つ機会が増えました。
マイホームの新築で、耐震性を重視した家づくりが当たり前となるのは、当然の流れと考えます。
特に南海トラフ地震で被害が予想される地域においては、その傾向は強いはずです。
ハウスメーカーは競うように高耐震性をアピールしていますが、建物だけでなく土地についても地盤の強さは見逃せません。
熊本県には2つの活断層がありますので、エリアの選択も地震リスクへの対応といえます。
耐震性の高さだけでは快適な暮らしは難しいため、ZEH水準の性能の実現と、暮らしやすさの視点を、バランスよく設計に落とし込むことをおすすめします。
熊本県の土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、熊本県で注文住宅を建築される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。