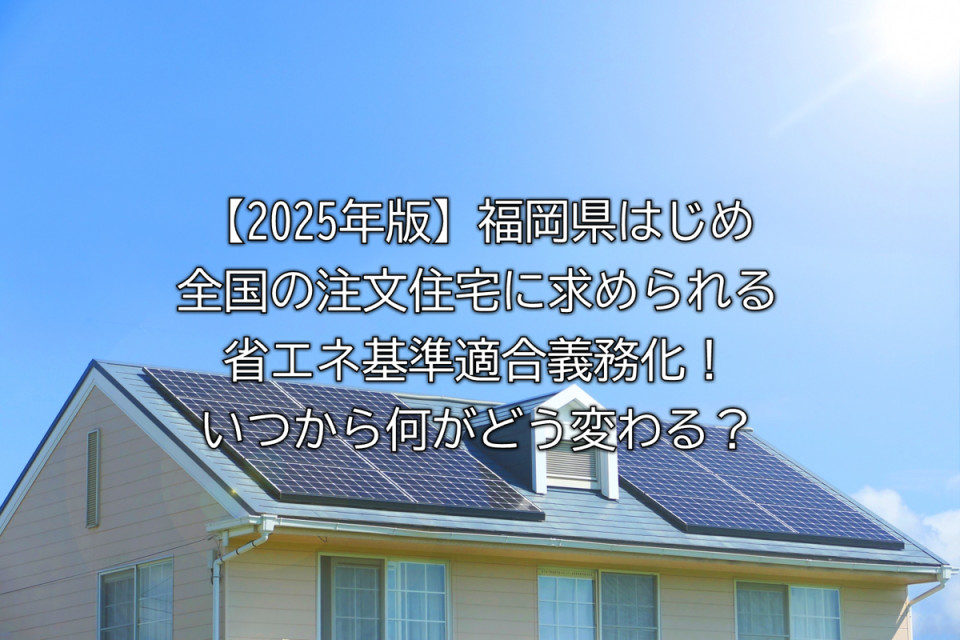
令和4年の建築物省エネ法改正で、2025年4月1日以降に着工するほぼ全ての新築一戸建て住宅は、省エネ基準への適合が義務となりました。
以前は、届出義務として建築主による省エネ計画の所管行政庁への提出で済んでいましたが、これからは省エネ基準に適合しているかの審査を受けることになります。
ここでいう建築主は注文住宅の発注者ではなく、ハウスメーカーや工務店、設計事務所などの事業者です。
この省エネ基準適合義務化が、注文住宅を新築したい人にとってはどのような影響があるのか気になるところでもあるため、背景や新築のポイントも含めて解説します。
省エネ基準に適合した住宅は、大手ハウスメーカーを中心にすでに供給されています。
エネルギー効率の良さから光熱費の削減が期待できますし、金融機関によっては金利の優遇を受けられるメリットもあり、省エネへの関心が高い層からのニーズに対応してきたからです。
ただし市場性だけではなく、日本が抱えるエネルギー問題を解消するためには、さらなる省エネ住宅の普及が必要との観点もあります。
省エネ基準適合義務化は、以下の2つの大きな目標のためのファーストステップに過ぎません。
2050年カーボンニュートラル
2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)
きっかけは2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標の強化が決定されたことです。
ゆえに、エネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での省エネ対策推進がカギとなりました。
さらに温室効果ガスの吸収源対策の強化として、木材需要の約4割を占める建築物分野での木材利用促進も含まれています。
樹木が大気から吸収したCO2は、伐採されて木材になっても取り込んだままという特性があり、木造住宅の増加はCO2削減に繋がるわけです。
2030年にはZEH水準へと基準が上がるため、その布石ともいえます。
適合義務化が求められる省エネ基準とは、建築物省エネ法で定められた基準(平成28年:2016年)のことです。
簡単に覚える場合は、一次エネルギー消費量等級、断熱等性能等級はともに4以上と認識してください。
等級については、それぞれ独自の計算によって決まります。
一次エネルギー消費量においては、BEI(Building Energy Index)という指標が使われ、詳細は専門的過ぎるため省きますが、以下の計算によって求めています。
BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量
この計算式で1.0以下になっていれば、省エネ基準を満たしていることになります。
外皮基準は、UA(ユー・エー:外皮平均熱貫流率)とηAC(イータ・エー・シー:冷房期の平均日射熱取得率)が指標です。
UA(W/m2・K)=単位温度差当たりの外皮総熱損失量/外皮総面積
ηAC=単位日射強度当たりの総日射熱取得量/外皮総面積×100
これらも詳細は省きますが、それぞれ地域区分別の基準値以下となることが必要になります。
少し触れましたが、2030年以降はZEH水準を満たした性能を確保することが国としての目標となっています。
前述した等級でいえば、断熱等性能では等級5と1段階上がり、一次エネルギー消費量に至っては等級6と2段階のアップです。
ZEH水準を満たすとなると、太陽光発電の搭載や蓄電池の導入も視野に入れざるを得ないと考えます。
太陽光発電や蓄電池について設置義務はありませんが、注文住宅も省エネ性能ありきとなれば、デザインやコスト面での影響も小さくないといえます。
太陽光発電を採用するなら、日当たりを考えると福岡県内での土地選びも重要です。

ハウスメーカーとしては、これまで供給していた住宅よりも高性能な建材の使用や設備導入、ベースとなる設計の直し、審査の事務作業増加など義務化への対応は済んでいると考えてよいです。
ただし、これから注文住宅を依頼する側にとっては、省エネ基準適合義務化がどう影響するのかまでは、なかなか想像できるものではありません。
よってこの章では、発注者の目線で省エネ基準適合義務化による影響をお伝えします。
省エネ基準適合については、定められた基準以上の高断熱かつエネルギー効率も同時に求められます。
例として挙げられるのは、以下の4つです。
外壁・屋根・床・窓などの断熱性能強化
断熱材の厚みを増す、または高性能な断熱材の採用
樹脂サッシや複層ガラス(Low-Eガラス)窓の標準装備
建物内の熱の伝わりやすさや逃げ(熱橋、ヒートブリッジ)対策の強化
空調・給湯・照明など、より省エネ性能の高いものを採用
高効率エアコンの設置
LED照明の標準化
高効率給湯器の採用
換気システムの導入
窓の配置と大きさへの配慮
過大な窓面積を避ける
方位による大きさの調整(北側は小さく高断熱、南側は日射取得と遮蔽バランスに配慮など)
日射遮蔽への配慮
庇やバルコニーの活用
外付けブラインドや遮熱フィルムの検討
緑化による日射調整
各ハウスメーカーによって基本設計は異なるため、省エネへの考え方に共感できるかどうかも重要です。
基本的には、住宅の外観や間取りを含めたプランニングについて、直接、制限されることはありません。
和風・洋風・モダン・北欧風など、どのようなデザインスタイルでも実現可能です。
ただし、省エネ性能を確保するためには、これまでよりも慎重な検討が必要になります。
例えば、リビングの大きな掃き出し窓や開口部は、断熱性能に大きく影響するため、高性能な窓の使用、冬の日射を取り込める南面に配置などの対応が考えられます。
吹き抜けは空間の広がりで人気ですが、暖気が上昇して冷暖房効率が落ちる可能性があるため、適切な断熱・気密施工や空調計画が重要です。
暖かみのある空間が欲しいときは無垢材が使われますが、床や壁は、断熱材との併用に工夫が必要な場合があります。
省エネ住宅に実績のあるハウスメーカーであれば、デザインと省エネ性能を両立させる提案ができます。
断熱材の増量や高性能断熱材の採用、高性能窓の使用などで、従来の仕様と比べて建築コストが上昇する可能性があります。
高効率設備の導入もコストアップの要因ですが、設備の小型化(例:断熱性能が向上することで必要な暖房能力が小さくなるなど)によって抑えられるケースもあります。
省エネ基準適合には、所定の審査が必要です。
審査の申請にかかわる人件費など、いわゆる間接コストの負担は免れないでしょう。
一方で、以下のような費用軽減要素もあります。
光熱費の削減
補助金や減税措置
維持・管理費用の軽減(結露やカビ発生リスクの低減による)
建築コストの上昇幅は、福岡県内の地域性や現在の標準仕様との差によって異なりますが、総建築費の5~10%程度を見込んでおけば、大きくはズレないと考えます。
既に省エネ基準に適合した仕様を標準としているハウスメーカーでは、コストアップも限定的である可能性は高いです。
省エネ住宅の初期費用と福岡県の土地取得のコストの予算配分には気を付けましょう。

省エネ基準適合が義務化以降、注文住宅においては、大なり小なりの影響を見据えて、家づくりの考え方を変えていくことも求められます。
ハウスメーカーにとっても、単純にコストアップを見積もりに反映させるようでは、客離れに繋がってもおかしくありません。
義務化をきっかけに、コストの優位性を含めて新たな受注競争がスタートしている面もあるため、改めて省エネ住宅を建てるポイントをまとめました。
普段は、物件情報サイトなどで省エネに関する情報を掴み、住宅展示場やハウスメーカー主催の相談会などで、直接、省エネ住宅に関する情報を仕入れると効率的です。
その過程で、省エネに精通したハウスメーカーをいくつかピックアップし、過去の実績や提案力、補助金申請サポートの体制などをチェックします。
その一方で、省エネ対応によるコスト増を見込んだ資金計画を立て、新たに住む福岡県内の自治体独自の補助金・助成金の有無についても調査しておくことをおすすめします。
最後は、住まいに求める要素の優先順位を明確にしておくことです。
注文住宅の魅力でもあるデザイン性を重視するのか、将来的な光熱費削減を重視して、より上位の省エネ住宅にするのかなど、価値観に基づいて判断できるようにしておきます。
省エネ基準はあくまで、現時点での最低限の基準です。
2030年にはZEH水準が基準になることが予定されているため、将来を見据えると、さらに上回るハイグレードな省エネ住宅を選択する価値はあります。
まず、候補として挙げられるのはZEHです。
高断熱・高気密・高効率設備に加え、太陽光発電などの創エネ設備を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にすることを目指した住宅です。
次に、長期優良住宅が挙げられます。
断熱性能に加え、耐久性や可変性、維持管理のしやすさなどで一定の評価を得て認定された住宅です。
トレンドを追うならば、GX志向型住宅がおすすめです。
ZEH以上の省エネ基準が求められる住宅で、脱炭素志向型住宅ともいわれています。
こうした上位基準の省エネ住宅は、初期費用は増加しますが、長期的には光熱費削減や健康維持、資産価値の保全などのメリットが期待できます。
また、今後のエネルギー価格上昇や環境規制強化のリスクに対する強みも、魅力のひとつです。
メインとして活用したいのは、子育てグリーン住宅支援事業です。
GX志向型住宅:160万円/戸
長期優良住宅:80万円/戸
ZEH:40万円/戸
GX志向型住宅はすべての世帯、長期優良住宅とZEHは18歳未満の子を有する世帯と夫婦いずれかが39歳以下の世帯が対象となります。
税制面においては住宅ローン減税、資金面では固定金利ですが一定期間金利優遇がある「フラット35S」など、負担を軽減する制度があります。

省エネ基準適合の義務化によって、省エネ住宅が当たり前の世の中になっていきます。
初期費用のアップは免れませんが、元々、省エネ基準に適合した住宅を提供していたハウスメーカーならば、大きな負担なく理想のマイホームが実現できます。
さらに光熱費の削減や資産価値の維持も付随してくる省エネ住宅は、暮らしやすさの向上も見込めるため、費用対効果は十分にあるといえます。
福岡県での土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、福岡県で省エネ住宅を建築される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。