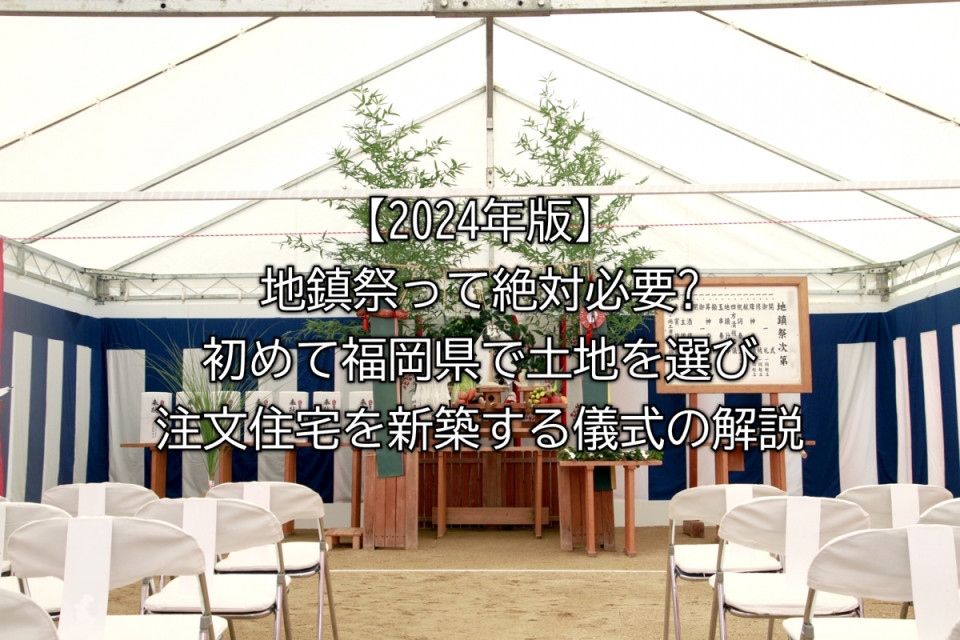
注文住宅の新築においては、安全祈願や土地の神様を祀るために、地鎮祭を行うことが一般的です。
ところが、コロナ禍での各種セレモニーの自粛、制限などが尾を引いているのか、地鎮祭が省略されるケースが増えています。
また、コストカットを理由に省略する建築主もいます。
法令で定められているわけではないため省略しても問題ありませんが、ハウスメーカーや工務店は、地鎮祭を実施する前提で新築の相談に応じていることがほとんどです。
ゆえに地鎮祭の実施については双方での話し合いの上で決定されるとよいですが、知識として地鎮祭の役割などを理解しておいても損ではありません。
この記事では、注文住宅を建築する際に行う地鎮祭について、その目的やメリット、デメリット、一般的な流れなどについて解説します。
地鎮祭は古くから行われている儀式であり、福岡県では地鎮祭を請け負っている神社が各地に点在しています。
ハウスメーカーや工務店は、地鎮祭の実施を推奨されることが多いです。
絶対的なものではありませんが、この機会に、
地鎮祭の歴史
実施の目的
注文住宅での儀式の意味
についてお伝えします。
建設コンサルタンツ協会(地鎮祭の歴史とその意義|一般社団法人 建設コンサルタンツ協会)によると、地鎮祭は691年持統天皇のころ、日本書紀において
「使者を遣して、新益京(あらましのみやこ)を鎮祭らしむ」
との記録があると書かれています。
また、伊勢神宮の社殿が建設された際にも地鎮祭は実施されており、
「鐵人像(てつひとがた)・鏡・鉾各40枚、長刀子(ちょうとうす)20枚、????4柄、鎌2張、小刀子(しょうとうす)1枚、鍬2口、五色薄絁(いついろのうすぎぬ)各1丈、木綿(ゆう)・麻各2斤」
を奉納したとされています。
現在では、竹や縄を用意するなど簡易的な内容になっていますが、形を変えながら現代まで続いている儀式です。
日本には地域を守る神様がいるとされており、土地を利用する際にはその神様に挨拶や感謝を示し、許可を得る必要があるとの考え方が現在でも残っています。
また、工事中の事故や災害が起こらないよう加護を願い、完成後の新居の安全を見守っていただくことも併せて祈願することが地鎮祭の主たる目的になります。
その他にも、土地のお清め、関係者とともに新築をスタートする区切りの意味もあり、気持ちよく着工するためにも重要なステップであることは確かです。
注文住宅での新築は、施主のこだわりが詰まった「理想の家」を形にする、一大プロジェクトです。
地鎮祭では、土地と住宅に対する感謝と祈りを通じて新たな生活の基盤を整える意味もあります。
ゆえに、
土地との調和を図る
理想の家づくりのスタートの象徴
家づくりの原点を思い出す機会
精神的な安心感
施主・施工業者間の意思疎通
といった付加価値が得られます。
これから福岡県で土地選びをスタートするなら、早い段階でお気に入りの物件を見つけておきましょう。

地鎮祭の歴史や目的、その価値について理解できたとしても、具体的なメリットを感じないという声もあります。
逆に儀式や祈願はメリットの有無で判断するものではないという意見や考え方は間違っているとはいえません。
対外的なものよりも、内面的な影響、例えば前述したような安心感や新築をスタートするという区切り、節目としての役割が大きいことも確かです。
それらも踏まえて、この章では地鎮祭のメリットとデメリット、さらに省略した場合の影響についてお伝えします。
地鎮祭は工事の安全を祈願する儀式の一面もあるため、ハウスメーカーや工務店のスタッフ、あるいは直接、工事を担当する職人にとっては気を引き締める、安心を得るという見方をします。
注文住宅の新築は、建築する側と施主側のチームワークが肝心ですから、一堂に会して地鎮祭を行うことは、滞りなく工事を進めるためには重要です。
また、一般的に注文住宅の新築ぐらいしか、自らのための地鎮祭を実施する機会が訪れることがありません。
つまり、日本の独自の文化を体験できることは、非常に貴重なことでもあります。
初めての経験として、家族や子どもにとっても良い思い出になり、単なる儀式以上の意味を持ちます。
地鎮祭には費用、いわゆる初穂料が必要です。
地域の相場や地鎮祭を依頼する神社によって、多少の違いはあるものの、おおむね3万円〜5万円ほど必要です。
さらに、米や酒、魚などの奉納品も用意することになるため、総額で10万円前後の金額を見積もることになります。
また、実施の日程次第では、平日が実施日になる可能性があり、仕事を休まざるを得ない状況も出てきます。
なぜならば、地鎮祭にふさわしい時間帯として、大安、友引、先勝の午前中が、候補として挙げられるためです。
土日祝日にスケジュールできればよいですが、調整が難しいケースもあります。
地鎮祭を省略することで、費用の負担と工数の削減が可能です。
その一方で、工事関係者や家族、ましてや土地の神様に対して、何か後ろめたさを感じてしまうことも考えられます。
一例として、地鎮祭を省いた結果いつの間にか新築の工事がスタートしてしまい、家づくりの実感が湧かなかった、少なくとも初日は立ち合いたかったという声もあります。
ハウスメーカーや工務店にすべてを任せられる信頼感とは別に、未来の住宅完成に向けての第一歩という節目もなく流れるよう工程が進むのも、少々物足りない印象はぬぐえません。
注文住宅は人生の中でも大きなプロジェクトですから、福岡県で好条件の土地に巡り合い、さらに地鎮祭での安全と安心の祈願は決して損ではありません。

地鎮祭は地域によって多少の違いがありますので、福岡県で一般的に採用されている手順と準備について解説します。
儀式の最中に慌てることがないよう、予備知識として事前にチェックしてください。
地鎮祭には12のステップがあり、1〜2時間かけて行われます。
この章では儀式の流れ、いわゆる式次第を紹介します。
|
儀式名 |
内容 |
|
入場及び開式の辞 |
地鎮祭の始まりとなる儀式。 |
|
修祓の儀 |
「しゅつばつのぎ」と呼ばれるステップで神職が大麻を左右に振って参加者の身を清める。 |
|
降神の儀 |
祭壇におかれた神を迎えるための依り代となる「神籬」に神様を迎え、全員起立して頭を下げる。 |
|
献饌 |
「けんせんのぎ」と呼ばれるステップで、祭壇に海の幸や山の幸をお供えする。このタイミングでは全員着席することが多い。 |
|
祝詞奏上 |
「のりとそうじょう」と呼ばれるステップで、神職が氏神様に建物を建てることを報告し、工事の安全と土地の利用について祈願する。 |
|
切麻散米 |
「きりぬささんまい」と呼ばれるステップで、土地の四方に神職が神酒とお米、お酒を撒いて清める。 |
|
地鎮の儀 |
施主が神職から鍬を受けとり、盛り砂を掘り起こすステップ。 |
|
玉串奉奠 |
「たまぐしほうてん」と呼ばれるステップで、次のような手順が定められている。 |
|
撤饌の儀 |
「てっせん」の儀と呼ばれるステップで、お神酒などのお供え物を下げる儀式。 |
|
昇神の儀 |
神籬のお供え物を神職が片付ける。 |
|
閉式の辞 |
参加者は全員起立し、地鎮祭の終了を神職が告げた後に施主が工事安全の挨拶を行う。 |
|
神酒拝戴 |
「しんしゅはいたい」と呼ばれるステップで、施主が参加者全員にお神酒を配り、神職の合図で乾杯する。 |
あくまでも一般的な流れのため、正確な情報はハウスメーカーや工務店、あるいは神社にお問い合わせください。
福岡県では、一般的に地鎮祭のお供え物(米、酒、魚など)は神社が用意してくれますが、それ以外にも竹、縄、盛り土、テントが最低限必要です。
これらの準備物はハウスメーカーや工務店が用意してくれますが、当日になって慌てることの無いよう、事前に相談しておくことをおすすめします。
地域ごとに準備物や手順が多少異なるため、あらかじめ神社またはハウスメーカーや工務店に、式次第を含めた段取りと費用を確認しておくことが重要です。
たとえば地鎮の儀は、地域によって掛け声をかけるケースがあり、事前に神職から説明を受けることになります。
また全員着席や全員起立のタイミングも、神社によって異なることがあります。
リハーサルなどは特にありませんが、当日、進行役である神主が式の直前に、儀礼の指導などをわかりやすくサポートをしてくれるため、必要以上に心配する必要はないです。

地鎮祭は工事の安全を祈願するだけでなく、着工が始まる重要な節目でもあるため、家づくりにこだわりがある場合は実施することをおすすめします。
福岡県では、多くの神社が地鎮祭を受付していますので、どのエリアで建築しても実施可能です。
ハウスメーカーや工務店に準備を依頼すると、かなりスムーズに進みます。
ただし地域によっては、施主が自ら準備をする、儀式の最中に行うべき手順などがあります。
地鎮祭を実施する際には、しっかりと手順と準備を確認しておくことが大切です。
福岡県の土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、福岡県で注文住宅を建築される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。