※本記事は農地転用について情報提供のみを目的としています。農地法を基にしたアドバイスや実務のサポートについては、行政書士など専門家にご相談ください。
熊本県は、熊本市を中心に市街化区域が展開されているものの、県土の利用状況(2016年)においては、総面積の約60%以上が森林、約15%が農用地で、宅地はわずか5%(熊本県の都市計画 2020)に過ぎません。
ゆえに、好条件での土地探しは、争奪戦というのが現状です。
このような背景から、地目が宅地ではなく田畑の土地を宅地に転用して家を建てる、いわゆる農地転用も少なくありません。
農業の人手不足や高齢化を理由に、農地をハウスメーカーや不動産業者が買い取って宅地として売り出す、あるいは子が家を建てるために親が譲渡するケースが、一般的と言えます。
そこで今回は、農地を宅地に転用して注文住宅を建てる際に、知っておくべき基礎知識や費用の相場、リスクなどについてお伝えします。
注文住宅を建てるための土地は、地目が宅地でなければなりません。
市街化区域の雑種地や山林であれば、家が完成した後に地目変更が可能なため、問題なく取引できます。
しかし田畑は、農地法で農業委員会への届出、もしくは農林水産省の許可が必要と定められており、違法転用となると3年以下の罰金もしくは300万円以下の罰金を科せられます。
ゆえに、農地の多い熊本県においては、農地転用も住宅用の土地を取得する手段のひとつと考えるならば、制度や費用について概要を知っておくとよいです。
農地転用の流れは、建築を検討している土地の都市計画区域によって異なり「市街化区域」か「市街化調整区域」かを調べておく必要があります。
都市計画区域が「市街化区域」の場合は、農業委員会に必要書類を提出するだけで許可を得ることができます。
ゆえに建築許可が得られる前提となるため、スムーズに家づくりを進めることが可能です。
市街化区域は、都市計画法において「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり、宅地に変更して住む人が増えることを優先していることも有利に働きます。
その一方で市街化調整区域は、農地や緑地の保全が優先される区域です。
4ヘクタール以内であれば農業委員会、4ヘクタールを超える場合は農林水産省の許可が必要となります。
注)1ヘクタール=10000㎡
許可を得るためには、農業委員会の聴取を受ける、多くの必要書類を提出するといったことから、稟議の期間が数ヶ月間におよぶことも珍しくありません。
つまり、農地転用を予定している土地が、どちらの都市計画区域に属しているかで、家づくりの計画が変わる可能性が高いため、事前に確認すべきポイントです。
農地を宅地に転用して、注文住宅を新築するための土地とする費用については、以下のような金額が相場となります。
|
費用がかかる項目 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
|
行政書士への報酬 |
4~5万円 |
3~30万円 |
|
書類入手にかかる費用 |
無償 |
1~2万円 |
|
造成費用 |
整地:1,000~2,000円/㎡ 造成:70,000~100,000円/㎡ |
|
市街化区域であれば、農業委員会へ書類を届けるだけで許可を得られるため、行政書士の報酬は市街化調整区域よりも安くなります。
さらに必要書類は、熊本県の公式ホームページ(農地転用許可制度について - 熊本県ホームページ)から、無償でダウンロード可能です。
その一方で市街化調整区域であれば、書類や農業委員会への意見陳述の工数がかかります。
また、親からもらい受ける農地が、農用地区域内にある場合は、「農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)」が必要です。
一部ではありますが、このような違いから市街化調整区域と市街化区域では、行政書士への負担が増すため、必然的に報酬が高くなります。
また、農地は一般的に道路よりも低い位置にあるため、土を入れて造成・整地をする必要があるため、造成費用についても資金計画に含めておくことが求められます。
ゆえに農地転用の必要が無い、熊本県の優良な土地の最新情報を検索して、住宅プランとセットで検討しておきましょう。
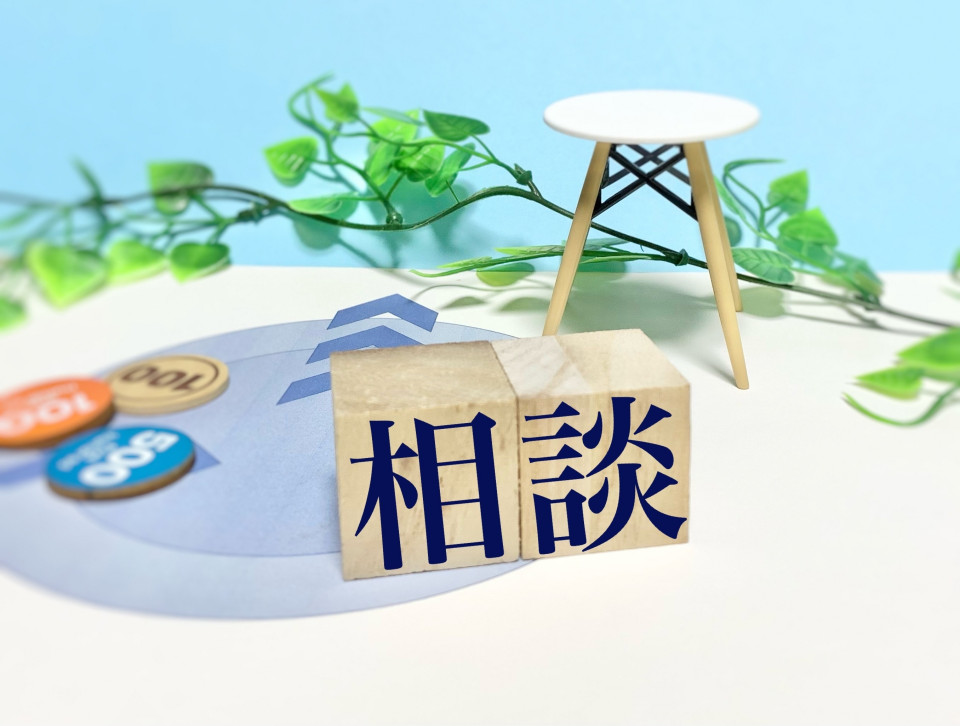
親から譲り受けた農地を宅地に転用して注文住宅を建てることは、そもそも住宅用の土地が少ない熊本県にとって、土地探しという工程をスキップした家づくりとして有効な手段のひとつと言えます。
ただし、許可申請などの手続き、費用負担もありますが、農地を宅地に地目変更する際には問題点の把握も重要なことです。
この章では、農地転用の問題点の中から、
について、お伝えすることにします。
まず、農地転用は誰がやるのか、つまり申請者についてのシンプルな疑問についてお伝えすると、状況によって異なります。
農地転用の許可申請は、
が基本です。
ちなみに第4条に相当する場合は単独申請、第5条に相当する場合は共同申請となります。
今回の記事では、親の所有する農地に、子が建築費用を負担して注文住宅を新築するというパターンをメインにお伝えしていますが、このケースでは第5条に相当するため、親子での許可申請となります。
親が所有する農地に、子の住宅を建てて住まわせる場合は、第4条に相当するため、親の単独申請が適切な流れです。
農地転用の許可を得た後は、地目変更の登記になります。
不動産登記法によって、変更があった日から1ヶ月以内に登記申請をしなければなりません。
では、変更とはいつのタイミングかと言えば、注文住宅においては、土地の造成を終えて、建築許可が下りたときが実務上合理的です。
ただし、状況により前後することもあるため、ハウスメーカーなどとよく相談することをおすすめします。
登記が終わり、田畑が宅地に変更されると、固定資産税等の税金が大幅に上昇する可能性もあります。
税金の変動については、税理士などの専門家に相談するようにしてください。
田畑は工作を目的とした土地であるため、一般的には上下水やガス管の引込はありません。
エリアによっては前面道路に本管すらないケースもあり、インフラ整備の費用として数百万円近くかかることもあり得ます。
そのため、親が持っている農地を転用して、家を新築する予定があるならば、付近に民家があるか、前面道路の埋設管状況などを、調査してもらうことをおすすめします。
もし、インフラ整備の工事が必要となれば、新築のスケジュールに影響が出る可能性は高いです。
田畑は道路よりも低い位置にあり、水が流れ込みやすい土地形状となっています。
熊本県は台風や豪雨の影響を受けやすい土地柄でもあるため、特に宅地造成については、慎重に行わなければ水害などのリスクを高めてしまいます。
また、農地は地盤が弱い傾向もあり、地盤調査も避けられません。
調査の結果、地盤が弱いとの結論となり、地盤改良工事も発生するとなると、資金的にも厳しくなることが予想されます。
農地が広いほど、問題の発生で資金計画を練り直すことも発生しやすいです。
地盤のしっかりした熊本県の土地を検索して、農地転用せずに新築するチャンスはたくさんあります。

地目が田畑の農地を転用して、注文住宅の建築を検討する際には、やはり、ある程度、リスクを把握した上で計画することをおすすめします。
一般的なリスクとしては、
が挙げられます。
農地転用の許可の基準は、
に大別されます。
転用したい農地が、市街化区域外の農地で、以下の農地区分にある場合は、立地基準において原則転用は不許可です。
第二種農地は、条件付きで転用が許可されることがあり、第三種農地は原則として転用の許可は下ります。
農地から転用された宅地は、一般の宅地と比べて住宅ローンの審査が厳しい傾向があります。
その理由は、主に以下の3つが挙げられます。
住宅ローンは、融資額と土地や建物の担保評価が釣り合う必要がありますが、農地から転用した宅地の価値は低く評価されることが多いです。
また、転用できたとしても買手が限られることから、一般的な宅地よりも流動性の面でマイナスになります。
農地を転用した宅地は法規制も多いことも含め、住宅ローン審査は厳しくなり、選択できる金融機関も限定されるリスクを抱えることになります。
親の農地を宅地に転用して家を建てる場合、近くに親が住んでいると、新築する住宅に対して、仕様やデザインなどの介入の可能性があります。
心理としては、自分の農地を差し出したのだから、意見する権利があるといったことが予想されますが、実際によくある話です。
このような介入は、完成後の実生活にもおよぶ可能性は高くなります。
ゆえに親子、嫁姑などの関係性が悪化する原因となりますが、介入しやすい距離で生活することに不安を覚えるのならば、地道に宅地を探すことがおすすめと言えます。

熊本県は県土の利用状況から、土地探しは争奪戦の様相のため、親からもらった田畑を宅地にして家を建てるケースも考えられます。
いわゆる農地転用ですが、
に関して、一般的な新築のプロセスとは別に、理解しておくことが大切です。
農地転用の手続きなどは、行政書士などの専門家に任せることが、最も合理的とも言えます。
当事者としてできることは、農地転用にかかわる費用を含めた資金計画です。
ハウスメーカーとともに情報を共有しながら、理想の家づくりに邁進することが求められます。
熊本県の土地(宅地)探しはリブワークのe土地netにお任せください。
また、熊本県で注文住宅を建築される方で、最新の土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。