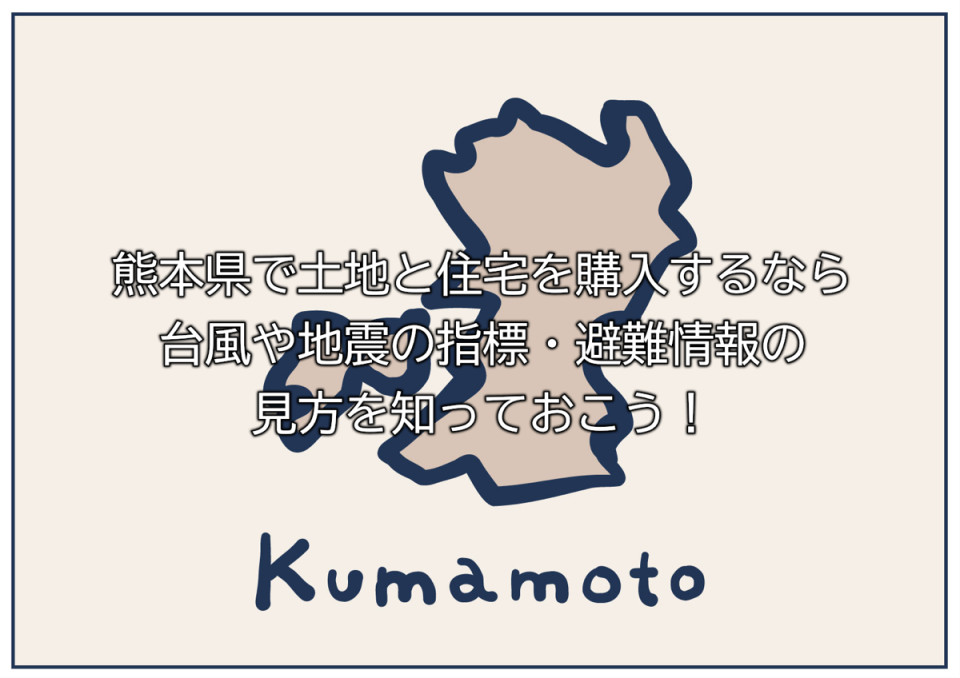
熊本県は九州の都市でも人口が多く、阿蘇山や天草といった人気の観光地を有しています。
特に熊本市を中心に繁華街があり、ドーナツ状に路面電車が配置されているため、車がなくとも生活できるエリアとなっています。
そのため、熊本県で土地を購入して注文住宅を建てる場合は、利便性の良い熊本市から検討されるケースが多いです。
しかし、熊本市は台風やゲリラ豪雨による洪水が懸念されるエリアとなっており、熊本市ハザードマップを参照すると、広い範囲を示しています。
この現状から、台風や地震の指標、避難情報の読み方を把握しておくことが重要と考え、本記事で説明することにします。
熊本県全域の災害・防災情報は、防災情報くまもとで調べることができます。
熊本市ハザードマップとの違いは、
などのメニューがあり、必要な情報が網羅されていることです。
熊本県は過去、熊本地震(平成28年4月14日、死者55人、負傷者1,814人)といった、非常に大きな天災に見舞われています。
ゆえに災害や防災についての感度を、高めておくことが求められます。
台風は春と夏に発生しやすく、春は低緯度からフィリピンの方向に向かい、夏は高緯度から日本に向かって北上する傾向が強いです。
そのような傾向から、夏は台風の被害が発生しやすい時期ですが、秋ごろになると秋雨前線の影響も加わり、大雨になりやすい季節となります。
台風に関する報道では「大型で強い台風」といった表現をしていますが、この表現方法は気象庁によって決められており、次のような定義があります。
〈風の強さ〉
|
階級 |
最大風速 |
|
強い |
33m/s(64ノット)以上~44m/s(85ノット)未満 |
|
非常に強い |
44m/s(85ノット)以上~54m/s(105ノット)未満 |
|
猛烈な |
54m/s(105ノット)以上 |
〈大きさの階級〉
|
階級 |
風速15m/s以上の半径 |
|
大型(大きい) |
500km以上~800km未満 |
|
超大型(非常に大きい) |
800km以上 |
なお、強風域の範囲が500km未満の場合は大きさを表現せず、最大風速が33/s未満の場合は強さを表現しません。
このように、報道を通じて台風の勢力を正しく把握できることから、上記の定義は覚えておてことをおすすめします。
地震においても、揺れの強さを表現する方法は気象庁が定義しており、次のようになります。
熊本地震では多くの死傷者以外にも家屋による被害も大きく、約16万棟の家屋が倒壊や半壊したそうです。
そのため、熊本県で家を建てるのであれば台風と合わせて地震に関する表現を知っておく必要があります。
|
用語 |
意味 |
|
まれに わずか 数量程度が非常に少ない。 大半 ほとんど |
極めて少ない。めったにない。 ほんの少し。 半分以上。ほとんどよりは少ない。 全部ではないが、全部に近い。 |
|
が(も)ある、が(も)いる |
当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数量程度の概数を表現できかねる場合に使用。 |
|
多くなる |
量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 |
|
さらに多くなる |
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われている場合に使用する。 |
一方、地震の震度においても定義があり、10段階のレベルで強さが定義されています。
また、どのくらいの強さなのかを日常生活に沿った表現となっていることから、震度を直感で知ることができます。
このことからも、熊本県で安心して暮らすのであれば地震の強さをすぐに判断できるように、以下の定義を覚えておくことをおすすめします。
|
階級 |
表現内容 |
|
震度0 |
人は揺れを感じない |
|
震度1 |
屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる |
|
震度2 |
屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる |
|
震度3 |
屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる |
|
震度4 |
ほとんどの人が驚く 電灯などのつり下げ物は大きく揺れる 座りの悪い置物が、倒れることもある |
|
震度5弱 |
大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる 棚にある食器類や本が落ちることがある 固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある |
|
震度5強 |
物につかまらないと歩くことが難しい 棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる 固定していない家具が倒れることがある 補強されていないブロック塀が崩れることがある |
|
震度6弱 |
立っていることが困難になる 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある ドアが開かなくなることがある 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある 耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがあり、倒れるものもある |
|
震度6強 |
はわないと動くことができない、飛ばされることもある 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる 大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある |
|
震度7 |
耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる 耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある 耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる |
台風や地震、大雨などが発生すると、避難情報がテレビやネットで速報されます。
避難情報では警戒レベルによって、取るべき行動が次のように定められています。
|
警戒 レベル |
状況 |
住民が取るべき行動 |
避難情報等 |
|
5 |
災害発生又は切迫 |
命の危険、直ちに安全確保! |
緊急安全確保 |
|
4 |
災害の恐れ高い |
危険な場所から全員避難 |
避難指示 |
|
3 |
災害の恐れあり |
危険な場所から高齢者等は避難 |
高齢者等避難 |
|
2 |
気象状況悪化 |
自らの避難行動を確認 |
大雨洪水注意報 |
|
1 |
今度気象状況悪化の恐れ |
災害への心構えを高める |
早期注意情報 |
住まいのエリアで避難情報が出た場合、現在、どのような状況なのかを客観的に見ることが重要です。
仮に、警戒レベル4が出たとします。
それでも自宅周辺は危険性を感じない、やり過ごせそうである、ましてや過去にも避難の必要がなかったとなると、今回も大丈夫だろうという考え方になりがちです。
状況は突然変化するため、警戒レベルには従うことをおすすめします。

防災情報くまもとによると、熊本市は、実は最も災害に弱いエリアである一方で、利便性は最も良い場所です。
つまり、熊本市で土地を購入して注文住宅を建てるのであれば、その場所のハザードマップを見ながら、リスクと利便性のバランスを検討する必要があります。
また、ハザードマップは数十年~100年に1度の大災害を想定したものであることから、実際に浸水したエリアかどうかを確認することも重要です。
そこで、この章では情報収集の手段として、SNSやアプリ、ハザードマップの使い方について解説します。
自然災害が発生した際は、現在の状況、過去の浸水などの被害に関する情報は、SNSやアプリで入手可能な時代です。
こうした情報ツールを駆使することで、より細かい、そしてリアルタイムでの災害情報を入手することができます。
ただし、SNSやアプリの情報はフェイクニュースも多いことから、なるべく国土交通省、気象庁、熊本県の各自治体が発信する情報を、優先的に入手することが重要です。
フェイクニュースは非常に巧妙化しており、悪質な内容も少なくありません。
実際に、2016年の熊本地震の際には、現在のX(当時ツイッター)で、熊本県内の動物園からライオンが逃げ出し、市街地の交差点を歩いているニセの画像が投稿されています。
このような突拍子もない情報は、自然災害の渦中では真偽を冷静に判断することは難しいものですが、一呼吸、二呼吸置いて、情報源を探ることが肝心です。
熊本県内での土地選びと注文住宅においては、自然災害と向き合うことを考慮して、少しでもリスクを減らせるエリアがおすすめです。
熊本市ハザードマップや防災情報くまもとは、熊本県内の災害情報をチェックするには最適なサイトです。
たとえば「洪水」と「津波」の両方に該当しないエリアを調べる、山間部での「洪水」と「土砂災害」を避けるエリアを捜索するなど、使い分けて活用できます。
国土地理院のデータがベースとなっていることから、最も信頼できる情報です。
スマートフォンやパソコンのブラウザから、すぐにチェックできるようブックマークしておくことをおすすめします。
もしくは、熊本県内の気象警報、注意報、土砂災害警戒情報、地震情報、河川水位情報をメール配信する、防災情報メールサービスへの登録も有効です。
防災情報メールサービスの登録は、防災情報くまもとから手続きできます。

熊本県で安全に暮らすのであれば、できるだけ強固な土地の上に注文住宅を建てたいところです。
災害に強い家の定義付けは一言では難しいですが、過去の熊本地震や熊本県の地震活動の特徴(※6)を考慮すると、やはり地盤の強さは無視できません。
地盤の強さの他には、自宅での数日の避難に耐えられることを、災害に強い家としてのポイントと考えます。
この章では、地盤の強さと在宅避難のポイントについて、それぞれ解説することにします。
災害に強い家とは耐久性はともかく、地盤の強さが何よりもカギです。
ジャパンホームシールドが公開している地盤サポートマップでは、
の4つを地図上で表しており、土地選びに役立ちます。
例えば、熊本市を含む熊本平野を対象に、地盤サポートマップで液状化の可能性をチェックすると、全般的に「やや高い」と判定されています。
ゆえに、地盤強化を視野に入れながら、土地探しをすることが重要です。
地盤をしっかり固めた上で、耐久性と耐震性が高い構造に強いハウスメーカーを選択することで、災害に強い家が得られます。
災害の規模や周辺の状況によっては避難ができず、在宅避難となるケースもあります。
そのようなリスクに備えて、普段から水や食料、太陽光発電での電力確保は、これからの時代は当たり前となっていくと考えられます。
省エネ住宅の推進により太陽光発電は必須となる流れのため、在宅避難のできる家作りという考え方が、これからは重要です。
後日、避難が必要となった場合に備えて、あらかじめ逃げやすい避難ルートを調べておくことも忘れてはなりません。
在宅避難は、せいぜい数日から長くて1週間程度と想定し、いかに避難所へ移動するまでに命をつなぐかという目的のもとで考えることが最適です。

熊本県で立地の良い場所、例えば熊本平野などは、ハザードマップで警戒すべきことが多いです。
ゆえに、台風、地震、避難に関する情報の読み方、さらにはSNSで情報を収集する際のデマの見極めを含めて、正しく理解、判断する術を知っておくことが重要になります。
安心して暮らすために、地盤の強さ、在宅避難への備え、さらに耐震性などの性能が高い注文住宅の3つの条件を満たせば、満足度が高まります。
熊本県で地盤の強いエリアでの土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、熊本県で新築一戸建て(注文住宅)を建築される方で、災害に強い住宅と土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。