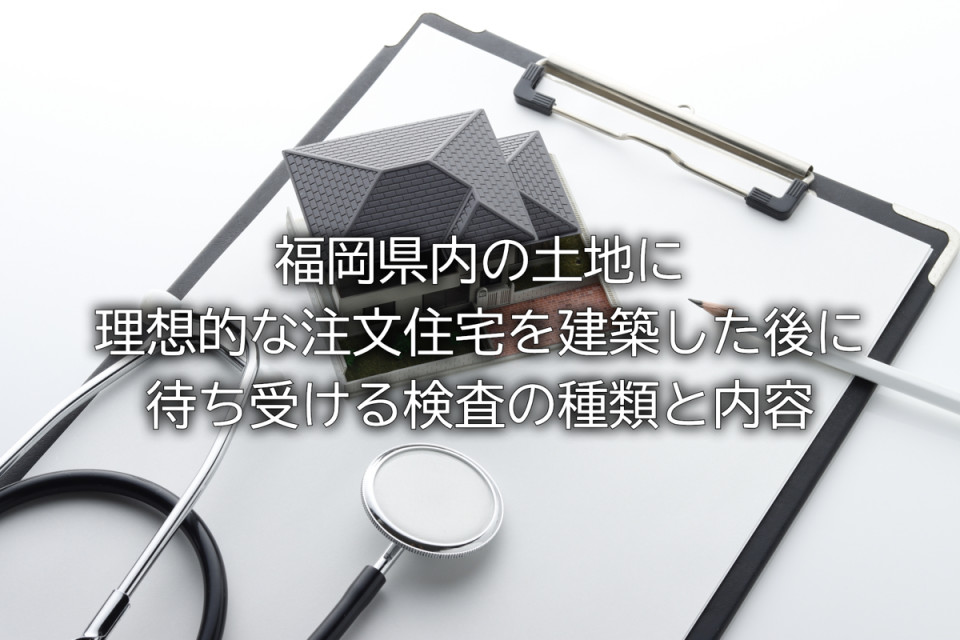
福岡県内外を問わず、注文住宅は完成後に検査を受け、安全で設計どおりに住宅が建築されているかを確認します。
検査は大まかに、
に大別されます。
そのため注文住宅を建てる際に、どのような検査を受けるのか、概要レベルでも知ることで、安心を得ることができます。
そこで今回は、注文住宅を建築した後に受ける検査について、種類と内容を詳しく解説します。
前述しましたが、福岡県内外を問わず注文住宅は、完成後に施主検査と完成検査を受け、クリアすることで引渡しとなります。
施主検査や完成検査とは何なのか、どこが実施するのかなど、それぞれの検査が持つ特徴について解説します。
注文住宅の工事発注者、つまりオーナーとなる施主が、建築の施工状態を確認するため、工事途中に行う検査です。
とは言え、オーナーとなる一般のお客さんは、建築知識がどうしても不足するため、実際はハウスメーカーや工務店などの建築施工業者がフォローすることになります。
このタイミングでは大まかなキズや汚れ、発注したとおりの工事が実施されているのかをチェックし、問題があれば建築施工業者に修正を依頼することができます。
前述したように、建築施工業者と施主の共同で実施することが多いですが、場合によっては工事管理者も同席することもあるため、気になる点は、直接、工事管理者に伝えられる点がメリットです。
建築工事が完成した後に、完成検査を実施します。
この検査が、修正を依頼できる最後のタイミングとなるため、気になる所を全てチェックすることが重要です。
主なチェックポイントは、次のようになります。
あくまでも一部ではありますが、チェックしたい部分は納得いくまで確認することをおすすめします。
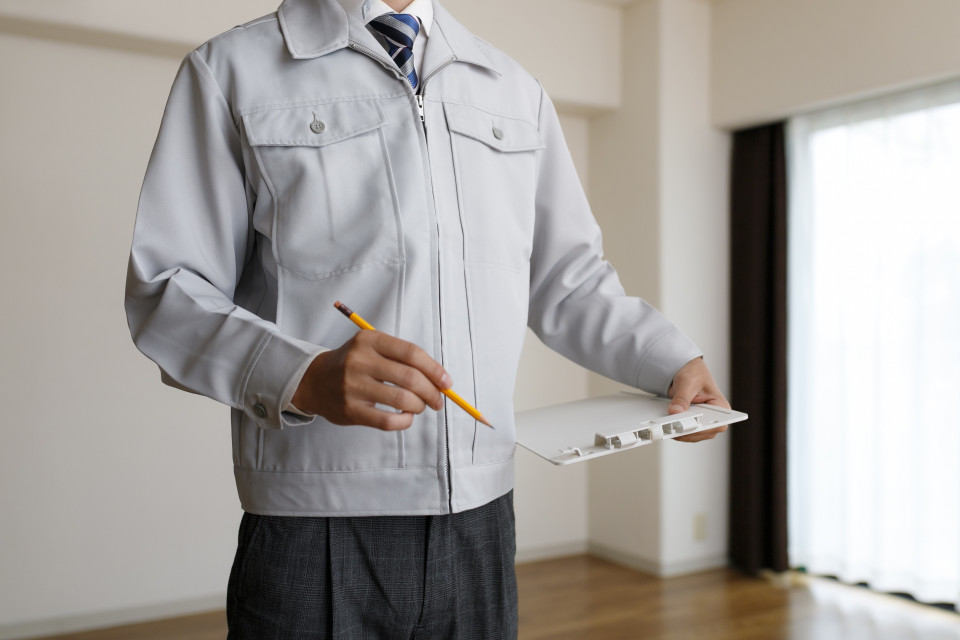
注文住宅は前述した建築施工会社と施主による検査を受ける前に、法や制度に基づいた検査を受けることになります。
これらの検査は、福岡県の市区町村が建築認可を判断するために必要なこと、施主にとってプラスとなる内容です。
この章は、法や制度に基づいた検査についての解説です。
建築基準法は国土交通省が定めた法律となっており、
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。
という文章が、第一条に記載されています。
このように法で定められていることから、建築基準法に基づいた検査は最低の基準ではありますが、それをクリアすることが義務付けられています。
なお、建築基準法に基づく検査は、
というステップで一般的に行われるものです。
福岡県に関しては、公式サイトで必要な書類などがダウンロードできるようになっているため、参考までにご覧になってみてください。
参照:建築物を建てる時などに必要な各種届出・申請書 - 福岡県庁ホームページ
建築基準法に基づく住宅よりも、さらに安全基準の高い住宅を証明する「住宅性能表示制度」を、国土交通省は設けています。
この制度は、平成12年4月1日に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいており、安全な住宅を建築するために設計段階と完成段階で、認定検査を実施するものです。
主に次の項目に基づき、国土交通省が認定した登録住宅性能表示機関によって検査されます。
設計段階での検査をクリアすると「設計住宅性能評価書」が発行され、完成段階では「建設住宅性能評価書」が発行されます。
瑕疵とは、目に見えないキズや破損のことを指し、雨漏りや白蟻被害、重大な木部の腐食などが代表的です。
引き渡しがあった後に、このような瑕疵が発生した場合、建築施工会社は対応する義務があります。
例えば不運にも、福岡県内で引き渡された住宅で立て続けに瑕疵が見つかり、修繕費用が多額になって建築施工会社が倒産という事態になると、修繕などの対応ができません。
その結果、施主が泣き寝入りしてしまうケースもあります。
このような事態とならないよう、住宅瑕疵保険に建築施工会社が加入していれば、保険会社が対応するしくみです。
これが住宅瑕疵保険と呼ばれるもので、新耐震基準の適合かつ既存住宅状況調査技術者の資格者が実施する、インスペクションをクリアすることで加入できます。
この保険加入で泣き寝入りリスクが抑えられ、大きな安心材料となります。
参考:保険の内容 | 住宅かし保険|JIO|住宅かし(瑕疵)保険の日本住宅保証検査機構
長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のことで、国土交通省によって定義付けされています。
長期優良住宅認定は着工前に申請し、完成後に次のような検査を受けることで認定を受けることができます。
福岡県内に土地を購入し注文住宅を建築して、長期優良住宅認定を受けると、補助金や助成金を受けられことがメリットなため、非常におすすめな制度です。

注文住宅の検査には、法や制度に基づいた検査以外にも、住宅ローンのフラット35を利用する際にクリアすべき検査と、住宅をトータルに診断検査するホームインスペクションがあります。
これらは第三者機関が実施する任意の検査として代表的なものです。
この章では、それぞれの特徴について解説しますので、ぜひ、参考にしてください。
福岡県内外で土地を購入して注文住宅の建築にあたって、住宅金融支援機構が提供している住宅ローンのフラット35を利用するには、適合証明検査を受ける必要があります。
この検査は、建築する注文住宅のスペックによって検査項目が変わりますが、通常の検査は「設計検査」と「竣工現場検査」の二本立てです。
ただし、注文住宅が「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」、「長期優良住宅」のいずれかを取得している場合は、竣工現場検査のみとなります。
このことからも、住宅ローンをフラット35で検討しているならば、あらかじめ注文住宅のスペックを頭に入れておくとよいです。
ホームインスペクションとは、住宅診断士が注文住宅をチェックし、キズや破損状態を診断する目的のもとに行います。
こちらは検査料を支払うことになりますが、全くの第三者機関での厳正なるお墨付きが欲しいときは、利用価値はあります。
もともと中古の一戸建て住宅のコンディションを多角的に専門家が診断して、購入予定者に説明するしくみです。
新築への診断も増加傾向であり、引き渡し直後の瑕疵、数年後に発覚する不具合など、将来のリスクについて備えるという目的で受診する価値はあります。
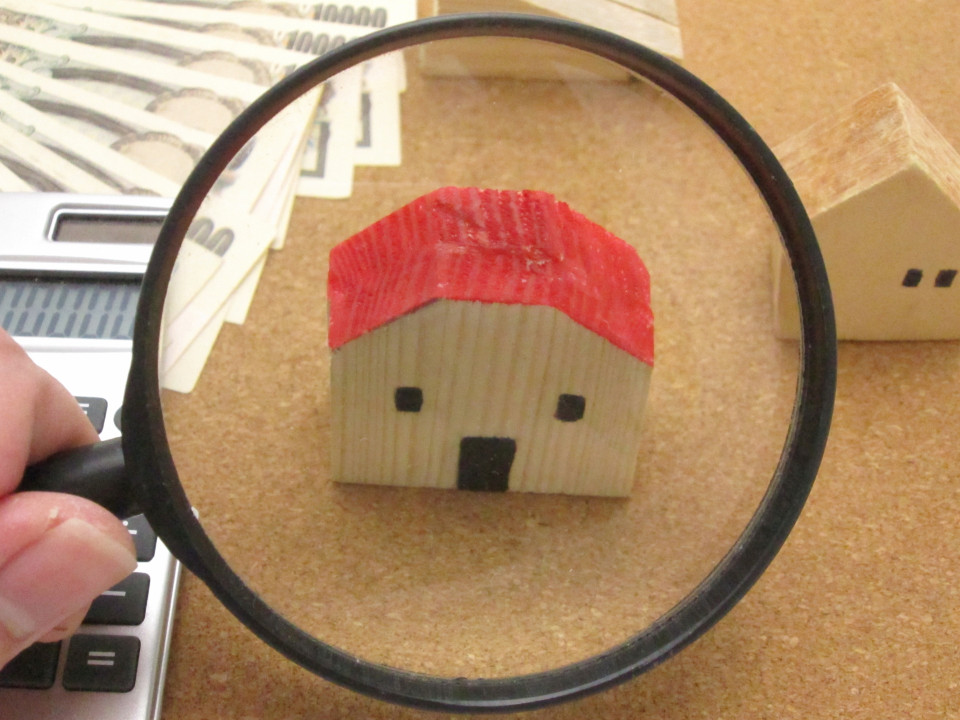
せっかく福岡県の良い場所で土地を見つけ、信頼できるハウスメーカーや工務店によって注文住宅を建築するとしても、施主にとって数々の検査は、不安材料となることもあります。
そのような不安は、やはり施主だからこそです。
そこで注文住宅の検査において、一般的によくある質問の中から代表的な内容を3つ挙げて、解説することにします。
施主検査と完成検査はどちらも引渡し前に実施しますが、施主検査については基礎工事と上棟のタイミングで1度実施し、完成後に再実施することもあります。
そのため、場合によっては施主検査2回と完成検査1回の、計3回になることもあります。
検査の時間は2~3時間程度が一般的です。
なお、施主検査のタイミングでは照明が設置されていない可能性もあるため、なるべく晴れた日中に実施したいところです。
施主は依頼人でもあるため、代金を支払う代わりに要望通りの注文住宅を建ててもらう権利があります。
前述したチェックポイントについて細かく確認し、少しでも気になる点があれば遠慮せずに質問することが重要です。
また、検査に立会う際には、できることならば図面やスケール、水平器、キズや汚れ部分の目印にするマスキングテープなどを持参して、積極的に参加することをおすすめします。
ハウスメーカーや工務店と内容を刷り合わせながら進めるため、任せきりでも良いですが、自主的に動くことでより検査がスムーズになります。

注文住宅が安心して引き渡されるまでに、さまざまな検査を受けることになります。
特に昨今の注文住宅は、省エネ基準の底上げなどハイスペック化が進むものと予想されます。
さらに住宅瑕疵保険などの制度利用にも検査のクリアが必要なため、少なくとも、どのような検査をするのか、事前に概要レベルでも把握しておくとよいです。
福岡県の土地探しはリブワークのe土地netにお任せください。
また、福岡県で新築一戸建て(注文住宅)を建築される方で、第三者機関による検査の相談を含めて、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。