住宅金融支援機構が運営するフラット35は、注文住宅を建てる多くの人にも利用されていますが、ここ数年、年齢層に変化が見られています。
住宅を建築する年齢によって、選択する立地や間取りが変わり、特に40代以上となると老後も踏まえて、快適な住環境と支出のコントロールも求められます。
そんなミドル世代は、返済額が定額となるフラット35との相性が良く、積極的に検討されている傾向です。
この記事では、ミドル世代が注文住宅を建てる上で押さえておくべきポイントと、フラット35の特徴について解説します。
ミドル世代と呼ばれる40歳以上の年齢層は、就職氷河期時代を経て、インターネットの導入時期から20年以上働いている世代になります。
特に20代後半から30代前半の時期には、リーマンショックによる金融危機、その派生による景気後退の影響も受けています。
そのため、将来への不安から結婚や家づくりが後回しとなり、40歳を超えて本格的に住まいを考える時期を迎えたケースも少なくありません。
こういった背景から、フラット35の利用者層も大きく変化しており、ミドル世代に対して融資を行うケースが増加しています。
住宅金融支援機構が公開している「2023年度フラット35利用者調査」によると、利用者の平均年齢とミドル世帯の全体構成比は次のように変化してきています。
|
|
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
|
平均年齢 |
40.0歳 |
40.1歳 |
40.2歳 |
40.3歳 |
41.5歳 |
42.8歳 |
44.3歳 |
|
構成比 |
42.9% |
43.3% |
44.2% |
44.9% |
49.6% |
53.9% |
59.1% |
データを公表した2013年では平均年齢が39.6歳、ミドル世代の構成比も39.7%でしたが、2014年には平均年齢が40歳を超え、2022年では構成比も50%を超えています。
各年齢層で最も高い割合を示すのは、2023年度の時点では30代ですが、統計の傾向から見れば、あと数年で40代が最多となるのも時間の問題です。
30代のうちに住宅ローンを利用し始めるケースが一般的だったのに対し、今後は40代以降でも遅くないという認識が浸透する可能性があります。
フラット35を利用する年齢層は高齢化が進んでおり、2022年から2023年にかけては、30歳代および30歳未満は減少傾向で、40歳代以上での増加が見られます。
全体でも40歳代以上は、59.1%とほぼ6割近くを占めています。
この背景としては、物価高に建築費の増大だけでなく、収入や支払い能力の面で、若年層では住宅の取得が難しくなっている状況も否めません。
40歳代以上ともなると、世帯によっては子が独立して自ら生計を立てられるようになっています。
そのタイミングで、夫婦だけの暮らしにあった住宅を手に入れ、返済計画も立てやすいフラット35の利用は合理的な行動ともいえます。
暮らしやすいエリアで公開されている、千葉県の土地と建物のセット返済例を見てみましょう。

注文住宅を建築する年齢層は統計によれば高齢化の傾向が見えます。
現にフラット35は、その性質上、ミドル世代の住宅ローンとして非常に適しており、しっかりと選ばれる理由があるのです。
この章では、フラット35がミドル世代に選ばれる理由を3つお伝えします。
団体信用生命保険とは、債務者が住宅ローン返済中に死亡もしくは重大な障害状態になってしまった場合、ローン残債の返済義務が免除される保険です。
一般的な金融機関では、この保険への加入が融資条件になっています。
フラット35では、この団信の加入は必須ではなく任意のため、健康リスクが高まるミドル層にとっては融資のハードルがないに等しく、治療中や完治してから間もない状況であっても審査の通過が期待できます。
ゆえにミドル世代は、少しでも有利であるフラット35を優先的に検討するケースも少なくありません。
ただ、未加入で万一のときは、ローンの残債はそのまま残り、遺族が引き継ぐことになります。
ゆえに団信については、多少の健康リスクを抱えていたとしても、加入を前提にしたほうが安心です。
さまざまな問題を抱えるミドル世代でも、フラット35では融資のチャンス、つまり審査の面では融通が利くことから人気があります。
リーマンショックやコロナ渦の影響による収入の減少を避けきれず、もとの収入水準を取り戻せないでいる人も少なくありません。
その結果、消費者金融からの借り入れや税金の滞納経験者は、若者世代よりも多くなっており、住宅ローン審査への不安を抱えている人も。
それでも審査がとおりやすいとされるのは、民間の金融機関と審査基準が異なリ、年齢で有利不利が出にくいためです。
さらに返済能力の評価や本人属性よりも、物件価値を重視する傾向も見えます。
ただし完済時の年齢は80歳以下になるよう設定しなければならないため、40代以上での借り入れは、どうしても返済期間が短くなりがちに。
また、親子でのリレー返済などもありますが、子に迷惑はかけられないという心情から、積極的には検討しない年代です。
ゆえに、定年退職後のローン返済力がカギとなります。
フラット35は固定金利のため、固定期間中は金利がどれだけ変化しても月々の返済額に影響がありません。
そのため返済の見通しが立てやすくなり、老後資金も計画的に運用できるメリットがあります。
ただしフラット35は変動金利よりも金利が高くなり、さらに返済期間によっても変動する特徴があります。
必然的に、毎月の返済額と総支払い額は変動金利よりも高くなってしまいますので、返済計画は念入りに行いましょう。
毎月の支払い例とともに、千葉県内の土地と建物をセットで公開中のサイトをご覧なって、返済のイメージを固めてください。

ミドル世代が土地を購入して家を建てる理由として、老後を快適に過ごすライフスタイルの実現があります。
快適さの定義は個人によって異なりますが、いくつか共通する傾向も見えてきますので、この章でお伝えします。
ミドル世代は、転職や転勤の可能性が若者世代よりも低くなるため、利便性を追求して都市部に住むより、ゆったりした生活を実現しやすい郊外を選ぶ傾向が高めです。
郊外の優位性は土地の価格にあり、都市部で販売している同等価格の土地と比較しても、駐車スペースや庭まで確保できる広さを得やすくなります。
建物も夫婦二人で暮らすには十分な間取りを持つ平屋をプランニングすると、トータルでかなりコストを下げられる可能性もあります。
収入が現役時代よりも下がることを考えると、非常に合理的な選択です。
郊外を選んだとしても、医療や介護施設へのアクセス、ライフインフォメーションの充実度、交通インフラの整備といった利便性も、ある程度は加味したいところ。
仮に、車移動がメインとなるような立地であれば、事故や運転能力の低下などのリスクを常に抱えねばなりません。
公共の交通機関、特にバスを第二の移動手段として常用できる環境が、望ましいといえます。
のどかな雰囲気と利便性のバランスを考慮して土地を選ぶことが、ミドル世代の家づくりにおいて重要です。
自然と都市機能のバランスのよい千葉県の郊外での土地を、今すぐ探してみましょう。

子が独立して夫婦二人の生活のほうが長くなるミドル世代では、若者世代とは住まいに対する方向性が少し異なります。
基本的な考え方としては、予算や住宅ローンに無理のない設計や、終の住処としての視点が重要です。
注文住宅では、自分たちのライフスタイルに合わせた間取りや設備を柔軟に選べる点が魅力です。
この自由設計を利点としてミドル世代向けに、将来を見据えた間取りを打ち出すハウスメーカーも少なくありません。
たとえばバリアフリーに対応した平屋住宅、階段を避けたワンフロアで完結する間取り、玄関から浴室までの動線をスムーズにする工夫などが挙げられます。
また、パントリーやランドリールームなど、十分な収納量も確保されるようになっています。
さらに、ZEH(ゼロエネルギーハウス)対応の省エネ設計、太陽光パネルの導入、断熱性能の高い窓や素材など、将来の光熱費を抑える工夫も重要です。
ミドル世代は子育ても終盤に差し掛かっている世帯も多いため、仕事・趣味・読書・動画鑑賞など、それぞれに没頭したい時間を確保しやすい状況です。
ゆえに個室または半個室の小さな書斎や趣味専用スペースを設けると、精神的なリフレッシュにつながります。
設計面においては、LDKを中心とした家族の空間と、個人の空間との間にワンクッションとなる廊下や間仕切りがあると、生活音や視線を気にせず過ごせます。
また、壁やドアの遮音性、窓の遮光性、テレワーク兼用の書斎なら防音対策は欠かせません。
そのほかには、バルコニーや中庭を、誰にも邪魔されない読書やティータイムの場とするアウトドアリビング的な発想も、個の時間を大切にする工夫のひとつです。
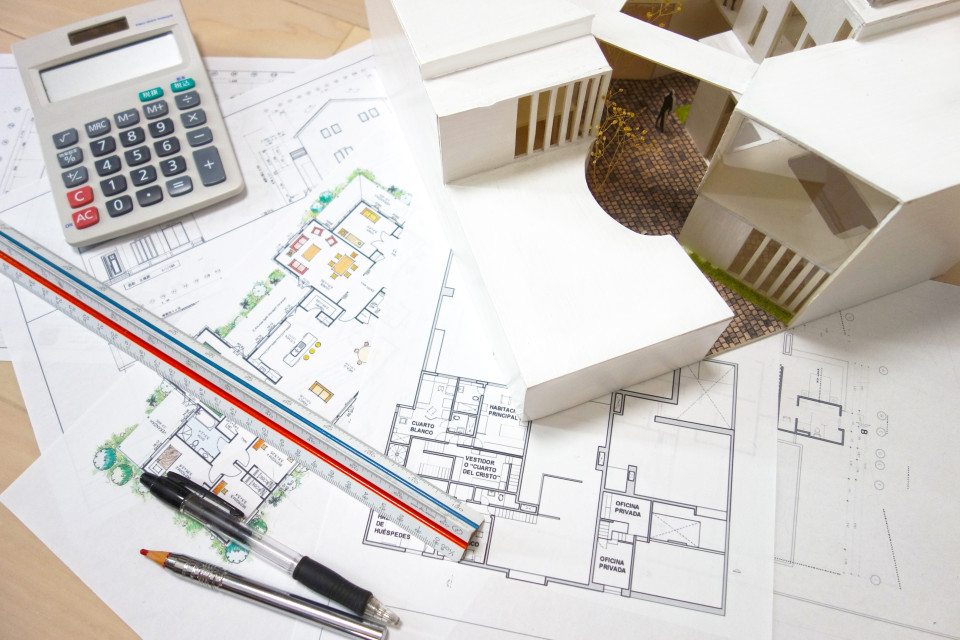
フラット35の利用者は、ミドル世代を中心に今後も増加する傾向が予想されます。
健康リスクや定年退職による収入減のリスクを抱えることになりますが、団信の加入が任意で月々の返済額が固定されているフラット35が支持されるのは、当然の流れといえます。
理想の家づくりについては、なるべく早い段階で金融機関や不動産会社、ハウスメーカーに相談し、納得できる資金計画と住まいをプランすることが重要です。
千葉県の土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、千葉県で注文住宅を建築される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。