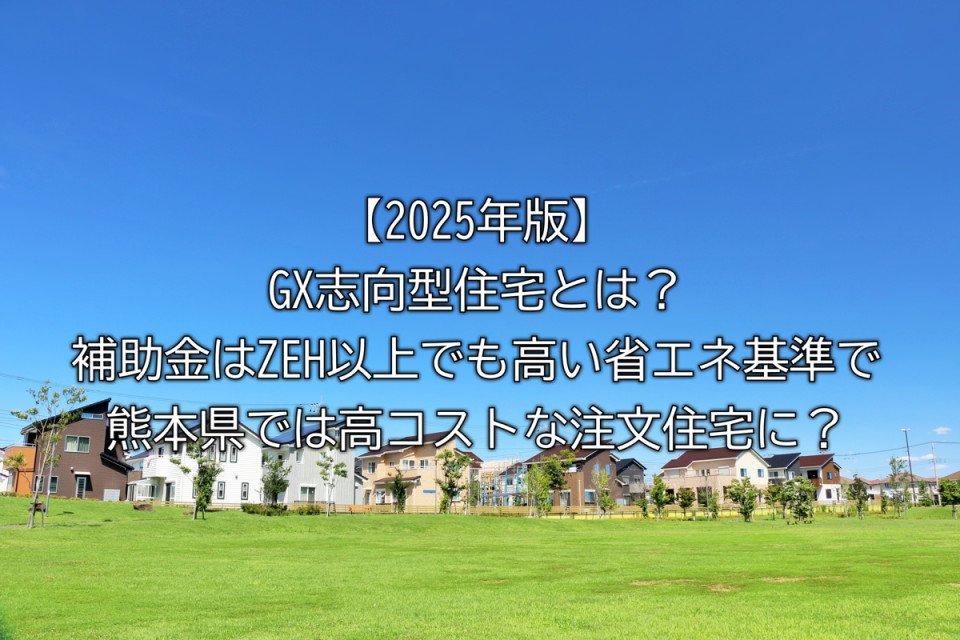
省エネ住宅といえば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、以下ZEH)が、一般的にはイメージされますが、新たに「GX志向型住宅」が加わります。
GX志向型住宅では、ZEH以上の省エネ基準が求められており、次世代の省エネ住宅として、熊本県内のハウスメーカーもキャンペーンを続々と展開中です。
そこで今回は、注文住宅の新たな選択肢となり得る、GX志向型住宅の特徴について解説します。
GXとは、グリーントランスフォーメーション(Green Transformation、以下GX)の略称で、再生可能なクリーンエネルギーを活用した脱炭素社会を目指す活動の枠組みです。
GX志向型住宅は脱炭素志向型住宅とも呼ばれており、省エネ住宅を普及させ、エネルギー問題を解消する一助とするため、国土交通省・環境省・経済産業省が連携して普及を支援しています。
日本政府は、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質ゼロにする)を目標に掲げています。
CO₂排出量を抑えるために住宅業界では、電力消費の削減や再生可能エネルギーの活用が進むよう、住宅仕様に落とし込むことが求められています。
そのひとつの取り組みが、GX志向型住宅の展開です。
GX志向型住宅の特徴としては、以下のようなことが挙げられます。
ZEH以上の断熱性能基準
高いレベルでの一次エネルギー消費量削減
HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)よるエネルギー管理
住宅ライフサイクルでの環境負荷低減
レジリエンス(災害に対する対応力・回復力)強化
GX志向型住宅とZEHにはどのような違いがあるのか、認定要件となる基準を比較すると以下の表のようになります。
|
省エネ住宅 |
断熱性能 |
一次エネルギー削減率(一般) |
|
GX志向型住宅 |
断熱等性能等級「6以上」 |
35%以上(再エネ除く) |
|
ZEH |
断熱等性能等級「5以上」 |
20%以上(再エネ除く) |
次に、それぞれの目的も整理します。
GX志向型住宅
省エネ性能向上(2050年カーボンニュートラル実現)
再エネ利用と高断熱化による脱炭素社会への貢献
ZEH
省エネと創エネによる年間一次エルネギー収支をゼロ以下
基準の数値以外は、建物の外観を見ても違いを認識しづらいわけですが、シンプルにZEH以上の省エネ住宅と考えると理解が早まります。
コスト面も含めて、どちらを選ぶか迷うところですが、基準をクリアするには、ほぼ太陽光発電システムの導入は避けられないのが現状です。
来たる2030年、省エネ基準はZEH水準がベースになること、以降の法改正でさらなる基準の変更まで考えると、GX志向型住宅を先取りする考え方もあります。
前述のように、次世代の省エネ住宅としてZEHよりも厳しい基準、太陽光発電システムの導入など、高機能化によるコストアップは避けられません。
初期費用が高くなる懸念もありますが、長期的な視点ではメリットも多い住宅仕様です。
補助金額の大幅アップ
光熱費削減効果への期待
暮らしやすさの向上
資産価値の維持(中古市場でのニーズが高い)
災害への対応力
詳しくは後述しますが、まずはZEH以上の手厚い補助金額が挙げられます。
予想される初期費用の高騰に備えて、資金計画では補助金の活用は欠かせません。
ZEHより高い断熱性能と省エネ性能を考えると、一般住宅と比較して年間の光熱費は大きく削減できると考えます。
気候の変化によって光熱費は上がる一方で、太陽光発電と蓄電池の導入で、発電した電力を効率よく自家消費に回すしくみができあがれば、家計の上でも大きなアドバンテージとなります。
環境に配慮した住宅は、補助金や税・金利の優遇措置を見ると、その資産価値への期待が伺えます。
また、台風・地震・豪雨などの自然災害発生時の停電に対する備えは、危機的状況の中にあって最低限の暮らしが確保できる意味でも重要です。
良い立地は資産価値に影響するため、熊本県内の省エネ住宅用の土地情報で、こまめにチェックしましょう。

一般論として、住宅の基本性能の向上と連動して、初期費用も負担が増します。
その原因は、省エネ性能の基準をクリアするために使用される建築材料や設備のグレードだけに留まらず、設計や施工面でもコストアップにならざるを得ないからです。
その一方、ランニングコストの低減や資産価値向上という、初期費用を回収するだけの経済的なメリットも期待できます。
GX志向型住宅では断熱等級6以上が求められるため、以下のような場面でコストアップが発生しやすくなります。
高性能断熱材の使用
高断熱サッシ・トリプルガラスなどの導入
外張り断熱による性能補填
高性能な玄関ドアの導入
熱交換型換気システムの導入
基礎断熱の強化
相場から推測されるコストアップ額は、一般住宅と比較して500万円前後です。
これに太陽光発電システムやエネルギー管理のためのHEMSを導入するとなれば、1,000万円近い金額になります。
補助金や税・金利の優遇措置で、カバーできる金額ではないからこそ、土地選びと資金計画は慎重になる必要があります。
高断熱で高気密、再生可能エネルギー活用のための設備導入によって、前述のように初期費用は高くなることは、想定しておかなければなりません。
予算が厳しい場合は、割安な土地を手に入れて、建物への資金を確保する調整が求められます。
それでも住宅部分にかかるコストは、住宅ローンの返済に影響します。
光熱費の節約が期待できるとはいえ、実際に住み始めてみなければ、住宅ローンの負担を軽減できるだけの効果が検証できないのが現実です。
さらに太陽光発電においては定期点検が義務付けされますし、経年劣化による部品交換や修理費用といった突発的な出費もあります。
短期的には負担は大きいですが、長期的な光熱費節約と資産価値によって、どの時点でプラスに転じるか、家計の収支シミュレーションで確認してみましょう。
ポイントとしては、以下の3つです。
相見積もり
補助金の適用(国や自治体の制度活用)
低金利の住宅ローン
すでに熊本県内のいくつかハウスメーカーは、GX志向型住宅のキャンペーンを展開しています。
2~3社ほどに絞って、相見積もりで妥当性を判断したいところですが、まだ、GX志向型住宅の相場などの情報が少ないのが現状です。
ゆえに、住宅省エネ支援事業者として登録しているハウスメーカーであれば、補助金(後述)の交付申請手続きもスムーズですし、詳しい説明も受けられます。
住宅ローンについては、低金利な変動金利に優位性がありますが、固定金利を希望なら一定期間適用金利が引き下がる省エネ住宅向けの「フラット35S」があります。
土地のつなぎ融資も考えているならば、熊本県内の土地相場を確認しておきましょう。
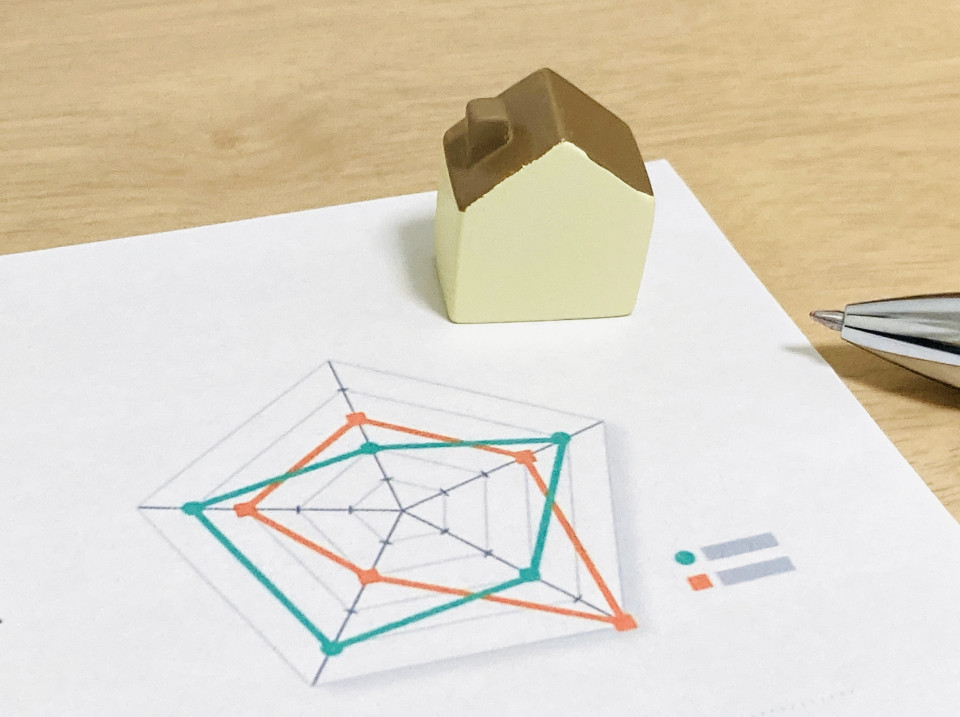
GX志向型住宅は、高性能な設備や仕様を採用する分、初期費用が割高になるため、国や自治体の補助金制度や住宅ローンの優遇措置の活用がカギとなります。
ただし、補助金や優遇制度には適用条件や申請期限があるため、事前にしっかりと情報を集め、ハウスメーカーや金融機関へ相談しながら、無理のない資金計画を立てることが重要です。
ここでは、GX志向型住宅の取得をサポートする補助金制度や金融商品の活用方法について解説します。
代表的な補助金制度として、「子育てグリーン住宅支援事業」があります。
長期優良住宅やZEH水準住宅に関しては、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが39歳以下)に限りますが、GX志向型住宅はすべての世帯が対象です。
現在の住宅を手放して、GX志向型住宅に住み替えを検討しているミドル・シニア層、子育てを終えた世帯も利用できます。
160万円の補助が受けられるため、各自治体独自の補助金制度も併用が可能であれば、初期費用の負担は軽減されます。
GX志向型住宅の導入コストを抑える、大きなメリットが得られる補助金ですが、依存した資金計画はハイリスクです。
補助金制度は、予算の上限に達すると受付終了になるため、申請のタイミングを逃すと支援が受けられません。
また、新築相談の場で補助金について過度に期待させ、GX志向型住宅の導入を迫るようなハウスメーカーにも要注意です。
弊社リブワークは、補助金申請のサポートを行っており、ZEHビルダーでもあるため、GX志向型住宅に対しても対応可能な体制になっています。
住宅ローンの優遇制度の活用次第では、総支払額を想定より抑えることもゼロではありません。
前章で少し触れた「フラット35S」は、省エネ性能の高い住宅を対象に、当初5~10年間の金利が引き下げられる金融商品です。
変動金利と比較すると金利の優位性は劣りますが、市場金利の上昇による返済額の増加を避けて、安定した返済計画を優先したい方に向いています。
都市銀行や地方銀行でも、環境配慮型住宅向けの特別金利ローンを提供している場合があるため、既に口座を開設している金融機関をチェックしてみましょう。

GX志向型住宅は、環境負荷の低減と快適な住環境の両立を目指す、次世代の住宅スタイルです。
脱炭素社会の実現に向け、政府の補助金制度や金融機関の優遇ローンも充実しており、導入のハードルは徐々に下がっています。
また、再生可能エネルギー技術や高断熱・高気密性の基準を上げたことで、ランニングコスト削減も期待されます。
一方で、建築コストやメンテナンス費用の抑制が課題で、長期的な資産価値の向上の保証もありません。
今後の技術革新と市場環境の変化を見据えながら、ライフスタイルも踏まえての決断が求められます。
熊本県の土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、熊本県でGX志向型住宅に関心がある方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。