
二世帯住宅には、親と子の世帯が一つの建物に共存しているイメージが一般的ですが、構造としては「完全分離型」と「部分共有型」の2種類に大別されます。
「完全共有型」を含めて3種類と説明されることもありますが、もはや同居との区別がつきにくい面もあり、本記事では対象とはしません。
完全分離型は、親世帯と子世帯それぞれの生活空間を完全に分けており、部分共有型は、玄関やリビング、浴室など一部の設備を共有する設計です。
どちらのタイプにもメリットとデメリットがあるため、二世帯住宅を建てる際には、事前知識として頭に入れておくことをおすすめします。
そこで今回は、二世帯住宅における完全分離型と部分共有型それぞれのメリットとデメリットについてお伝えします。
完全分離型は、二つの建物が縦並びもしくは横並びに建築されているような構造になります。
玄関をはじめ、生活空間は完全に分かれているものの、屋根や壁は繋がっていることから、敷地内に2棟の住宅があるケースと違い、お互いの生活環境は近いことが特徴です。
完全分離型二世帯住宅は、それぞれの世帯が快適に暮らせるよう、プライバシー空間が維持されます。
ライフサイクルが異なる世帯の場合は、生活音が聞こえないように対策する必要がありますが、完全分離型であればマンションのような構造になるため、気にすることなく生活することが可能です。
若者世帯の夫婦がともに仕事にプライベートに忙しく、時間軸がシニア世帯と違いがあったとしても、お互いに影響は小さくて済みます。
同居が敬遠される理由としては、生活環境が全く同じであるため、どちらかが気を使いながらの生活を余儀なくされることが挙げられます。
家族だからと、プライバシーが無視されるケースも想定されるため、トラブルが発生することも少なくありません。
その点、完全分離型の二世帯住宅であれば、それぞれの世帯が自由に行き来できない構造となっており、距離感に対するストレスは軽減されます。
たとえ家族であっても、世帯ごと、または個人でもライフサイクルが異なることは、珍しいことではありません。
個が尊重される時代において、二世帯住宅であれながらも自由な暮らしが可能なのは、完全分離型の大きなメリットです。
若者世帯が子育て中であれば、一時的にでも、シニア世帯に子どもの面倒を、安心して任せられる点も魅力の一つといえます。
自由さのある暮らしと、同居生活の良い所を集めたような生活環境は、完全分離型ならではといえます。
完全分離型の二世帯住宅は、早かれ遅かれ、片方が空き家になる可能性はあります。
その際の活用としては、
別の家族を住まわせる
第三者に賃貸する
といったことが考えられます。
賃貸については、住宅ローンの契約内容や管理をどうするかといった、クリアすべきことはありますが、活用の自由度も高いこともメリットです。
二世帯住宅が建築可能な熊本県内の土地情報が欲しいときは、市町村別にくまなく見ることをおすすめします。

完全分離型の二世帯住宅には、
建築費用の増加
土地スペース(広さ)の確保
過剰なコミュニケーション
といった点に、不安を覚える人は多いです。
よくあるデメリットとしても挙げられますが、これらについて少し詳しくお伝えします。
完全分離型は、注文住宅の二棟分ほどの建築コストがかかる前提で、相談や見積もりを取ることになります。
つまり、資金計画を慎重に検討しなければ、住宅ローンの返済で苦しくなる可能性は高いです。
そのため、二世帯間でのコスト負担だけでなく、借入金額や自己資金、返済期間、金融機関選びなど、明確にしておかなければ揉めることになります。
また、間取りや設備についての最終的な決定権、予算と支出の調整役などを決めて、なおかつ共有できていなければ、資金の枯渇や満足度低下の原因にもなります。
二世帯を並列に建築する場合、広い土地が必要です。
上下階で分ける縦列での建築よりも、土地面積は倍、購入費用もそれに準じるイメージとなります。
また1階をシニア世帯、2階を若者世帯とした場合であっても、エリアによっては建築制限によって希望する住宅仕様が実現できないこともあり、土地選びは難しい面はあります。
ゆえに、ハウスメーカーと住宅仕様を相談して、必要な土地の面積を割り出してもらうとよいです。
完全分離型とはいえ、住宅間の距離としてはゼロといっても過言ではありません。
毎日のように好き勝手に訪問されるような、過剰なコミュニケーションが生じる可能性もあります。
建築前に取り決めたお互いの訪問ルールを、入居後に反故にされるケースは珍しいことではないです。
訪問される側が共働きなど、日中が留守ならば影響ありませんが、どちらかが在宅しがちならば、ストレスの原因ともなります。
入居した後で「約束が違う」としても後の祭りです。
二世帯が仲良く暮らせるよう、熊本県の駅近や郊外の土地情報を見て、新生活をイメージしてください。

部分共有型の二世帯住宅は、一部の住宅設備を両世帯で共有するスタイルです。
どこを共有するかは両世帯で相談になりますが、完全分離型とは違うメリットがあります。
それぞれの世帯が積極的にコミュニケーションを取りたい場合は、部分共有型がおすすめです。
キッチンやリビングを共有して、主なコミュニケーションの場所とすれば、必要な情報の共有も可能になります。
子育てや介護が必要なケースでは、部分共有型の方が効率的になります。
水回りや玄関、廊下など、共有部分が多ければ、その分は完全分離型よりも建築コストを抑えられます。
本来、各世帯に必要な設備や空間を1世帯分でカバーする、いわゆるシェアハウスのような雰囲気ができあがりますし、その分、個室や収納を広く取ることも可能です。
特に、単体でも高コストな水回りを共有することで、設備費用や配管工事費を抑えられます。
並列の完全分離型よりも広さを必要とせず、駐車スペースと庭の大きさ次第では、一般住宅と変わらない土地面積でも建築が可能です。
ゆえに、都市部の立地や利便性を重視したい世帯には向いています。
傾斜地や高低差のある土地がお手頃価格で売り出されていることもありますが、個性的な二世帯住宅を望まなければ、造成費用の負担を考えると避けた方が無難です。
予算に応じた熊本県内の土地情報を、しっかりと掴んでおきましょう。

部分共有型の二世帯住宅で生活する際は、どうしても、
プライバシー
生活習慣
ランニングコスト
についてのトラブルが起こりやすくなることが、デメリットとして挙げられます。
共有部分が多くなれば、ある程度のプライバシーは共有されることになります。
実の親子関係ならば特に違和感を覚えないのかもしれませんが、義理の親子関係であれば、感じ方や許容の範囲、受け取り方などは全く異なってきます。
ゆえに、自室以外に人の気配がする環境でストレスを感じやすい気質ならば、そもそも部分共有型には合っていないと考えるのが一般的です。
シニア世帯と若者世帯が半ば共同生活になると考えると、食事や入浴、睡眠のタイミングにズレは生じるのは、事前に想定されることです。
ゆえに計画の段階で、ある程度は生活習慣のズレについて認識を共有する必要はありますが、実際に入居してから、想定と違う状況が出てきます。
しばらくは一堂に集まる場所で、些細なことでも話し合う機会を持つことが重要です。
お互いが小さな不満を蓄積するだけでは、何の解決にもなりません。
通常、住宅の新築に必要な費用と維持のためのランニングコスト、さらに生活費や税金の支払いなど、家計に関することは夫婦のどちらか、または共同で管理します。
ところが部分共有型の二世帯住宅は、両世帯での家計の負担に関する合意形成が非常に難しい、あるいは難航するケースがよくあります。
単純に折半するとしても、決して公平、平等とはなりませんし、突発的な支出が必要になる場面でも、都度、相談の上で進めなければなりません。
数年ごとに負担割合を見直すなど、熊本県内に好条件で土地を購入する以前に、双方でしっかり取り決めすることをおすすめします。

完全分離型と部分共有型の二世帯住宅では、所有権と住宅ローンについて、疑問や不安を覚える人もいます。
将来、売却や賃貸、もしくは相続といった節目を迎えたときに、勘違いや誤解を避けるためにも、一部でも基礎知識として頭に入れておくとよいです。
基本的には、
単独登記
シニア世帯、若者世帯のいずれかの所有として登記する
共有登記
出資の比率に応じた共有割合で登記する
例、「2分の1 土地太郎、2分の1 土地次郎
区分登記
完全分離型のみ可能な複数人による登記
の3つが挙げられます。
単独登記は、住宅の購入または建築契約を代表した人の名義となり、非常にシンプルで分かりやすいです。
要注意なのは区分登記で、住宅仕様において構造や機能が、それぞれ分離独立していることが認められなければなりませんし、登記の際の司法書士への報酬は、2世帯分を必要とします。
が、住宅ローン控除などの税制で有利な面もあるため、ハウスメーカーや金融機関に相談や確認の上で、登記の方法を選定することをおすすめします。
代表的な住宅ローンの組み方としては、
二世帯での収入合算による方法
親子でのペアローンを組む方法
親子でのリレーローンを組む方法
の3パターンとなります。
収入合算では借入枠が大きくなるため、ある程度の建築コストをカバーできますし、節税効果も高まりますが、連帯保証人は合算した相手のため、返済が滞ったときの対処については、金融機関にしっかり確認するようにします。
親子でペアローンを選択する場合、どちらも団信加入ができるため、どちらかが亡くなったとしても残債の負担はなくなります。
ただし審査と諸費用は、それぞれ必要です。
親子のリレーローンは、シニア世帯(親)がまずは負担し、その後、若者世帯(子)に引き継ぐ返済方式となります。
ただし、引き継ぎタイミングの予定にズレ、団信は若者世帯(子)のみが加入、若者世帯(子)が先に亡くなってしまったときの支払いなど、やや、考慮すべきことが多い印象です。
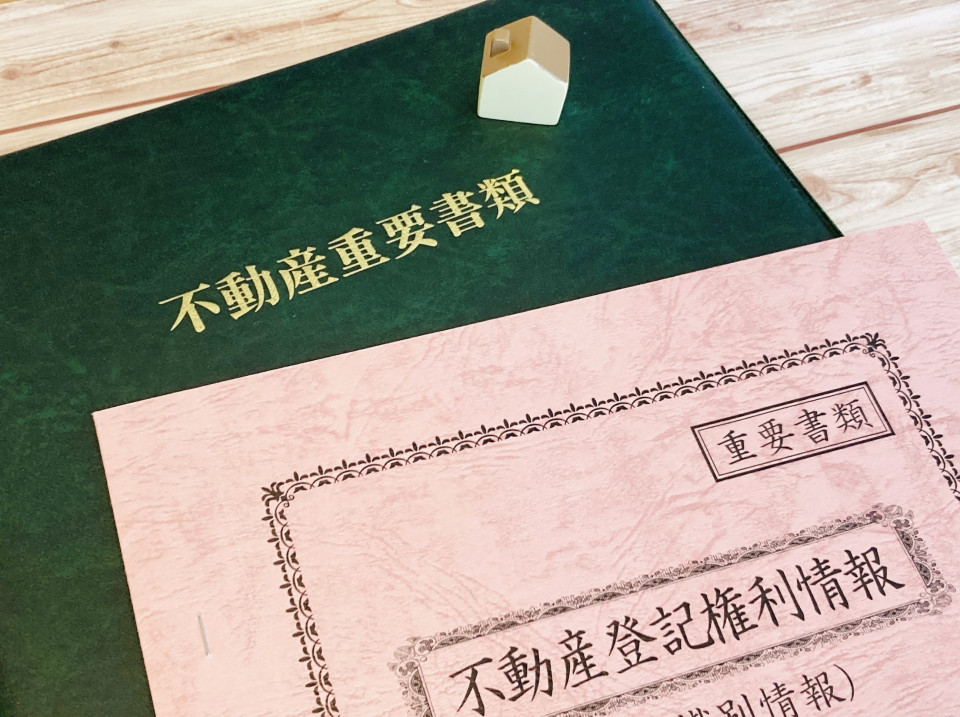
二世帯住宅を建てる際には、完全分離型と部分共有型のどちらであったとしても、メリットとデメリットを踏まえ、両世帯での合意形成がもっとも重要です。
多大な時間をかけてでも、ひとつひとつ、懸念事項は解消しておくことをおすすめします。
二世帯住宅の経験豊富なハウスメーカーであれば、さまざまな相談に対応することができますし、権利や資金的なことは、ファイナンシャルプランナーや不動産会社にアドバイスをもらうと、早い段階で問題も解決できます。
熊本県での二世帯住宅向けの土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、熊本県で二世帯住宅を注文住宅として建築したい方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。